|
仛 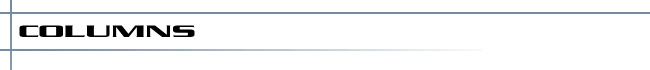 仛丂丂暥復偺傑偠傔搙悢偍榣傃丒怴擭丒怴偟偄偙偲丒blog弮寜偲儗僢僥儖揬傝丒僩僀儗寍弍仛仛仛 楌巎偲惗偒傞壙抣丄嶦偝傟偨戝巊丄巰偦偺傕偺仛仛仛 嶦奞幨恀偺儕傾儕僥傿丄僀儔僋偺怱棟揑嫍棧丅仛仛仛 傂偒偩偟偺楒仛仛 戝妛惗妶丅彨棃丅偗偠傔丅仛仛 僴儘僂傿儞丄抦揑愥偐偒丅仛仛 寍弍偲妛栤偺偪偑偄仛仛仛 搶戝屻婜崌奿暅尦摎埬偺僙儖僼島昡丅仛仛仛仛 椪彴怱棟妛傪巙偡丄偲偄偆偙偲偵偮偄偰丅仛仛仛仛 嵟埨儗儞僞僇乕丄敪尒丄昁尒両仌妛惗偑帠屘傞偙偲偵偮偄偰丅仛仛 慜偺楒恖傪乽朰傟傞乿丠仛仛 乽儕傾儖乿偲偼偳偆偄偆姶妎偐丠乧乧僀儔僋愴憟偐傜峫偊傞嘆仛仛仛仛 嬯擸偲桙偟偺暥柧揑堄枴 嘇仛仛仛仛 嬯擸偲桙偟偺暥柧揑堄枴嘆仛仛仛仛 僷儚乕億僀儞僩偺僗僉儖傪峫偊傞仛仛仛仛 偮傑傫側偄惗偒曽偲偼側偵偐丠仛仛 偲傝偁偊偢丄擔婰宍幃偺傕偺偼丄 Diary-column-blog乮Genxx.blog*乯偵堏峴偟傑偡丅側偺偱丄偙偺怴偟偄儁乕僕偼崱傑偱偺偙偺儁乕僕偲傎傏摨偠栶妱傪壥偨偡偙偲偵側傞偲巚偄傑偡丅 偨偩丄偙偺崱偺儁乕僕偵偼崱傑偱偺夁嫀儘僌偩偗偠傖側偔丄傑偨僐儔儉傪捛壛偡傞偙偲偵側傞偲巚偄傑偡丅偮傑傝丄偙偙偵偼傑偲傑偭偨暥復傗僐儔儉傪嵹偣偰偄偔偙偲偵偟傑偡丅偦傟偱偼丅 偱傕儔儀儖揬傝偼彮偟婋尟偐傕偟傟側偄丅儔儀儖乮儗僢僥儖乯揬傝偲丄嵎暿偼丄巻堦廳偩偐傜偩丅偙傫側偙偲傪峫偊偨偺偼丄偒偭偲崱擔惛恄昦偵偮偄偰峫偊偰偨偐傜側傫偩傠偆偗傟偳傕丅摑崌幐挷徢乮惛恄暘楐昦乯丄鏝烼丄懳恖晄埨徢側偳丄偝傑偞傑側怱偺昦偑偁傞偲偄傢傟偰偄傞丅偱傕偙傟傜偼丄愄偐傜懚嵼偟偨傢偗偠傖側偄丅愄偼丄偙傟傜偺昦婥偵帡偨傛偆側徢忬傪帩偮恖傕丄幮夛偺拞偱丄偦傟側傝偵帺傜偺億僕僔儑儞傪摼偰曢傜偟偰偄偨丅寛偟偰丄乽惛恄昦堾乿側傞傕偺偵妘棧偝傟偰偄偨傢偗偠傖側偄丅彮側偔偲傕丄乽昦婥乿偲偄偆傕偺偼丄幮夛揑偵宍惉偝傟偨傕偺偩丄偲偄偆偙偲偑戝帠偩丅傑傢傝偑昦婥偩昦婥偩偲憶偑側偗傟偽丄杮恖偑乽帺暘偼昦婥偩乿偲偄偆偙偲傪帺妎偡傞偙偲偼側偄丅 偟偐傕乽昦婥乿偲偄偆丄堦尒壢妛揑側憰偄傪偟偨儔儀儖乮儗僢僥儖乯偼丄怣溸惈偑嫮偄偩偗偵丄僞僠偑埆偄丅杮奿揑偵摫擖偝傟偮偮偁傞僗僋乕儖僇僂儞僙儕儞僌偩偭偰丄偨偲偊偽晄搊峑偺巕偵丄杮摉偼妛峑偵栤戣偑偁傞応崌偱傕丄斵帺恎偵栤戣偑偁傞偲偟偰丄乽怱偺昦乿偲偄偆儗僢僥儖傪揬傝晅偗丄栤戣夝寛偺僼儕傪偟偰偟傑偆婋尟惈偲忢偵椬傝偁傢偣偩丅傑偨傾儊儕僇孯偺愽悈娡偵傛偭偰捑杤偝偣傜傟偨偊傂傔娵偺帠審偩偭偰丄搟傝偲斶偟傒偵恔偊僴儚僀偵摓拝偟偨擔杮懁偺堚懓偵懳偟偰丄傾儊儕僇孯偼乽僇僂儞僙儔乕乿傪弨旛偟偰懳墳偟偨傜偟偄丅乽昦婥乿偲偄偆儗僢僥儖傪揬傜傟丄帺暘偺搟傝斶偟傒憺偟傒偲偄偆姶忣傪梷偊偮偗傜傟傞偙偲傎偳丄儉僇偮偔偲偄偆偐嵟埆側偙偲傕側偄丅 乽昦婥乿偼幮夛揑側傕偺偩丅偨偲偊偽丄挬偵嬀偱帺暘偺巔傪3暘埲忋尒傞恖偼丄帺堄幆夁忚偲偄偆怱偺昦偱偁傞丄偲偄偆愢偑偲偮偤傫椡傪帩偭偨偲偟傛偆丅嬀傪傛偔尒傞恖偼丄3擭屻偵偼栻傪張曽偝傟傞傛偆偵側傝丄10擭屻偵偼擖堾傪嫮偄傜傟傞偐傕偟傟側偄丅僫儖僔僗昦丅偁傝偊側偄偲傕偄偊側偄丅側偵偑昦婥偱丄側偵偑昦婥偠傖側偄偐傪寛掕偡傞偺偼丄幮夛偺拞偱桳椡偲側傞尵愢乮棟榑乯偲偦傟傪嶻傒弌偡尃椡側偺偩丅帺暘偵堷偒偮偗偰峫偊傞偲丄偲偰傕嫲傠偟偄婥暘偵側傞丅 懠恖偺怱偺掙偐傜偺嫨傃偵丄娙扨偵儔儀儖乮儗僢僥儖乯傪揬傞傋偒偠傖側偄丅偄偪偳棫偪巭傑偭偰怺偔峫偊偰傒傞昁梫偑偁傞丅儔儀儖乮儗僢僥儖乯傪揬偭偨傎偆偑壗昐攞傕恖惗傪妝偵夁偛偣傞偩偗偵丄偙偺偙偲偵偼忢偵拲堄偟側偔偪傖側傜側偄丅偠傖偁丄偁偊偰乽弮寜愰尵乿偵棫偪巭傑偭偰峫偊偰傒傞偲丄側偵偑尒偊偰偔傞丠偦傟偼師夞偺偍妝偟傒偵丅  丂 丂 傆偩傫僩僀儗偵帩偭偰傞僀儊乕僕乮婛惉奣擮亖儗僢僥儖乯傪暍偟偰偔傟偨傾乕僩嶌昳丅擔忢偺儗僢僥儖傪偳傫偳傫曵偟偰偔傟傞偺偑寍弍嶌昳偺柺敀傒丅嵍懁偺偼丄幚嵺偵傇偭偐偗偰偒偨偗偳丄埆偔側偐偭偨乨徫丂偄偢傟傕Mori-art-museum強廂
斵偺乽惗偺嵀愓乿偼丄偦傟偧傟偺怱偺拞偵崗傒崬傑傟傞丅怱偺拞偵崗傒崬傑傟偨斵傪丄乽杮乿偲偄偆丄巰屻傕巆傞儊僨傿傾偵傑偲傔傞恖偑偁傜傢傟傞偐傕偟傟側偄丅偁傞偄偼塮夋偵側傞偐傕偟傟側偄丅恖娫偲偄偆傕偺偼丄偙偆偟偰丄帺暘偑惗偒偨帪戙偩偗偱偼側偔丄屻乆偺帪戙偱傕惗偒懕偗傞偙偲偑偱偒傞丅 僫億儗僆儞偺傛偆偵丄慡悽奅拞偺恖娫偺怱偺曅嬿偱惗偒懕偗偰偄傞恖娫傕偄傟偽丄壌偺慶晝偺嬥抝傒偨偄偵丄恊懓偺娫偱偢偭偲岅傝宲偑傟偰偄偔恖娫傕偄傞丅乽巰乿傪偒偭偐偗偵丄偁傞恖暔偑僗僩乕儕乕壔偝傟傞丅偙偺僗僩乕儕乕偼丄偝傑偞傑偵宍傪曄偊側偑傜丄楌巎傪偢偭偲惗偒懕偗偰備偔丅偢偭偲丄偢偭偲丅傕偪傠傫丄偄偔偮偐偼偳偙偐偱徚柵偟側偑傜丅懡偔偺恖偼丄帺暘偺巰屻傕丄帺暘偑僗僩乕儕乕偲偟偰楌巎傪惗偒懕偗偰備偔偙偲傪朷傫偱偄傞偼偢偩丅偦傟傕丄彮乆戝偘偝偐傕偟傟側偄偗傟偳嶁杮棾攏傒偨偄偵丄戝偒側僗僩乕儕乕偲偟偰丄偨偔偝傫偺恖偺怱偺拞偱惗偒懕偗偨偄偲婅偭偰偄傞偼偢偩丅側偵偐戝偒側偙偲傪惉偟悑偘偨偄偲偄偆栰朷丅崅峑偺偙傠偵乽儅儖僋僗傪挻偊偰傗傞偤乿側傫偰偆偦傇偄偰偨帺暘偑夰偐偟偄偗偳丄怱偺偳偙偐偱偼丄崱偱傕傑偩偦傫側椶偺栰朷偑偔偡傇偭偰偄傞丅 偱傕丄曣偑岅偭偨尵梩偵偼偭偲偟偨偙偲傕偁傞丅偆偪偺恊晝偼擼偺戝摦柆釒仺2擭屻乮尰嵼乯偼敀寣昦偲廳昦傪孞傝曉偟偰偄傞偗偳丄偦傫側晝傪丄愄偼帺桼杬曻偩偭偨曣偼丄偢偭偲巟偊偰偒偨丅偦偺宱尡傪傕偭偰丄岅偭偨尵梩丅乽惗偒偰偄傞娫偵丄扤偐堦恖偺惗偒偑偄偵偙偙傑偱側傟傞偭偰偙偲偼丄偡偛偄偙偲側偺偐傕偟傟側偄傛丅偦傟偩偗偱傕丄偡偛偔惗偒偨壙抣偑偁偭偨偺偐傕偟傟側偄乿 偨偲偊偽帋尡丅偨偲偊偽僾儘僕僃僋僩丅偨偲偊偽丄偢偭偲巚偄昤偄偰偄偨彨棃偺柌丅傂偲偮偺偙偲偵嵙愜偟偨偭偰丄偦傟偱偡傋偰偑廔傢傝偠傖側偄丅惗偒傞壙抣丄偭偰傕傫偼丄埬奜帺暘偑梊憐偡傜偟偰偄側偐偭偨偲偙傠偐傜揮偑傝崬傫偱偔傞偺偐傕偟傟側偄丅恖惗偼偍偦傜偔丄帺暘偑僀儊乕僕偟偰偄傞傛傝丄偢偭偲姲梕偩丅偩偐傜丄忕択偩偲偼巚偆偗傟偳巰偸側傛両乮朸桭払傊乯 仴恖偺巰偑乽僗僩乕儕乕壔乿偝傟傞偲丄乽巰乿偦偺傕偺偑帩偮埑搢揑側朶椡惈偑塀偝傟偰偟傑偆丅偙偺奜岎姱偺巰偩偭偰丄乽旤択乿乽塸梇択乿偲偟偰岅傜傟傞婋尟惈傪廫暘偵帩偭偰偄傞丅偩偐傜偙偦丄偦偺慜偵乽巰乿偦偺傕偺偺埑搢揑側懚嵼偵拲堄傪岦偗傞偨傔偵丄12/01偺僐儔儉偱丄巰懱偺幨恀偵儕儞僋傪挘偭偨偺偱偟偨丅乽巰乿偲岦偒崌偆丄偲偄偆偙偲偼丄偨偩乽巰乿傪僗僩乕儕乕壔偡傞偲偄偆偙偲偲偼堘偆丄偲帺暘偼巚偭偰偄傑偡丅偦傟偩偗偵偲偰傕擄偟偄丅偪側傒偵丄僀儔僋偺栤戣偵偮偄偰峫偊傞偲偒丄僥儘崙壠僀僗儔僄儖傊偺帇揰傕愨懳偵朰傟傞偙偲偼偱偒側偄偱偟傚偆丅  丂丂丂丂 丂丂丂丂 堦曽丄榋杮栘偗傗偒嶁偼丄斶偟偄傑偱偵壐傗偐側丄憮敀偄搤偱偟偨 偦偺僀儔僋偱傕偮偄偵擔杮恖奜岎姱偑嶦奞偝傟偨乮僯儏乕僗乯丅偦傟偱傕傑偩傑偨僀儔僋偼墦偄丅抧棟揑偵傕丄怱棟揑偵傕斵曽偵偁傞丅崱偙偙偵丄傾儔僽宯偺儊僨傿傾偼曬偠偰偄傞偗偳丄擔杮偺儅僗僐儈偼帺庡婯惂偟偰偄傞偲巚傢傟傞幨恀偑偁傞丅嶦奞偝傟偨奜岎姱偺巰懱幨恀偩丅堚懓偺曽偺偙偲傪峫偊傞偲丄擔杮偺儅僗僐儈偺帺庡婯惂傕偁傞掱搙懨摉側敾抐偩偲傕巚偆丅偨偩丄傂偲偮偺慖戰巿偲偟偰丄偙偺幨恀傪傒偰恀寱偵僀儔僋栤戣丒傾儊儕僇庡摫偺乽僥儘愴憟乿丒偦傟偵懳偡傞帺暘偺僗僞儞僗偵偮偄偰峫偊傞偺偑丄嶦奞偝傟偨奜岎姱偺曽傊偺恀潟側岦偒崌偄偐偨偱偁傞偲傕巚偆丅 偦偺幨恀乮嬯庤側曽偼尒側偄偱偔偩偝偄乯 愄側傫偐偺彫愢偱撉傫偩偙偺戜帉偼丄偄偮傕帺暘偺怱偵廳偔偺偟偐偐偭偰偄傞丅偄傗丄偄偄偐偘傫側惈奿偩偐傜偙偦丄尵偄暦偐偣傛偆偲堦墳傕偑偄偰偄傞丅 恖偼偄傠傫側傂偒偩偟傪帩偭偰惗偒偰偄傞丅帺暘偱奐偄偨丄偁傞偄偼扤偐偵奐偐傟偨傂偒偩偟偺悢偩偗丄恖惗偺怓崌偄偑慛傗偐偵側傞丅奐偒奐偐傟偨傂偒偩偟偺傂偲偮傂偲偮偵丄偁偨傜偟偄悽奅偑媗傑偭偰偄傞丅傕偺傪巜偱悢偊傞偙偲偟偐抦傜側偐偭偨彫憁偑丄晝偵悢帤傪嫵傢偭偨丅傕偺偼柍尷偵奼偑偭偨丅壞偺奀偟偐抦傜側偐偭偨彮擭偑丄桭払偵僗僲儃傪嫵傢偭偨丅搤偺愥尨偲惵嬻偑偲偮偤傫斵偺栚偺慜偵傂傜偗偨丅抧曽偱惗傑傟堢偭偨妛惗偑丄忋嫗偟偰塮夋娰偵擖傝怹偭偨丅寍弍偺廳偔摡悓偝偣傞傛偆側悽奅偑斵傪廝偭偨丅 恖偼偄傠傫側傂偒偩偟傪帩偭偰惗偒偰偄傞丅傑偩奐偐傟偨偙偲偺側偄丄偨偔偝傫偺傂偒偩偟傪恎偵拝偗偰丄傂偲偮偱傕懡偔偺傂偒偩偟傪奐偙偆偲傕偑偒側偑傜丄偁傞偄偼帺暘偠傖奐偔偙偲偺偱偒側偄側偄傂偒偩偟偑扤偐偵傛偭偰奐偐傟傞偙偲傪婅偄側偑傜丄枅擔傪惗偒偰偄傞丅 偒偭偲丄乽楒乿偭偰傕偺傕偙偺乽傂偒偩偟乿偲娭學偟偰傞丅帺暘偑憡庤偵偲偭偰堦斣戝愗側懚嵼偩偲擣傔偰偔傟傞丄偦偺恖丅偦偟偰丄帺暘偵偲偭偰傕偦偺恖偑堦斣戝愗偱丄惗偒偑偄偺戝晹暘偵側偭偰偔傟傞丄偦偺恖丅乽偦偺恖偺懚嵼乿偲偄偆傂偒偩偟偼丄偨傇傫丄堦斣乽戝偒側傂偒偩偟乿丅偙偭傄偳偔怳傜傟偰丄偦偺乽戝偒側傂偒偩偟乿傪堷偭偙敳偐傟偰丄挿偄偁偄偩怱偑嬻摯偩偭偨丅幐楒偟偨屻丄偄傠傫側戙傢傝偺傂偒偩偟偑傗偭偰偔傞偗偳丄僒僀僘偑崌傢側偐偭偨傝丄嵽幙偑堘偭偨傝丄尒偨栚偑僀儅僀僠偩偭偨傝丄僴儊偨偲偙傠偱偟偭偔傝偙側偐偭偨傝乨 偱傕丄傂偒偩偟偼偦傟偩偗偠傖側偄丅偦偺偙偲傪朰傟偨傜晠偭偰偟傑偆丅乽戝偒側傂偒偩偟乿傪楒恖摨巑偱堷偒偁偄偭偙偟偰丄偦傟偩偗偵枮懌偟偰傞偲丄儂儞僩偵晠傞丅晄巚媍偩丅楒偭偰偺偼偨傇傫丄偍屳偄偵怴偟偄傂偒偩偟傪師乆奐偒偁偭偰偄傞偲偒偵丄偆傑偔偄偔丅乽偦偺恖乿偵怗敪偝傟偰崱傑偱尒側偐偭偨塮夋傪娤偨傝丄帺暘偺惗偒曽傪尒捈偟偨傝丅攚怢傃偟偰捝偄栚偵夛偭偰丅偱傕丄偙偺乽憡庤乮偦偺恖乯偺怴偟偄傂偒偩偟傪奐偔乿偭偰偺偼丄娙扨側偙偲偠傖側偄丄傔傫偳偄丄偟傫偳偄丅偼偠傔偺偆偪偼丄帺暘偑偨偩懚嵼偡傞偩偗偱丄憡庤偺乽戝偒側傂偒偩偟乿傗乽怴偟偄傂偒偩偟乿傪偑偟偭偲奐偗傞偐傜偄偄偗偳丄偟偽傜偔偨偭偰儅儞僱儕壔偟偰偔傞偲丄堄幆揑偵傗傜側偄偐偓傝丄憡庤偺怴偨側傂偒偩偟傪奐偔偙偲偼偱偒側偄丅 桭忣偲垽忣偺堘偄偵偮偄偰丄偨偟偐傾儕僗僩僥儗僗偼偙偆偄偭偨丅桭忣偼奜偵奐偐傟備偔娭學惈偩偑垽忣偼撪懁傊偲暵偠偙傕傞娭學惈偱偁傞丄偲丅暵偠傜傟偨娭學偺拞偱丄憡庤偲偺楒恖娭學偲偄偆乽戝偒側傂偒偩偟乿偵娒偊偰偟傑偆丅娭學偑晠傞丅乽戝偒側傂偒偩偟乿偩偗傪庣傞偙偲偵幏拝偟偰丄憡庤傪懇敍偽偭偐偟偰丄偁傞偄偼憡庤偵梫媮偽偭偐偟偰丄寢嬊側偵傕梌偊偰偄側偄乮亖偁偨傜偟偄傂偒偩偟傪奐偄偰偄側偄乯帺暘偵婥偯偔丅乽壌偼傕偆側偵傕偍傑偊偵梌偊傟側偄偺偐乨乿丂夛榖傕丄帺暘偨偪偺娭學偵偮偄偰偺僩乕僋偽偭偐偵側偭偨傝丅婥偯偄偨偲偒偵偼丄傕偆抶偄丅憡庤偼偡偱偵晠偭偨娭學偵寵婥偑偝偟偰乽戝偒側傂偒偩偟乿偡傜傕偼傗婡擻偟側偔側偭偰傞丅 仴帺暘偼偙偺夁偪傪側傫傋傫傕孞傝曉偟偰偒偰丄側傫傋傫傕幐偄偨偔側偄傕偺傪幐偭偰偒偨丅憡庤偑乽戝偒側傂偒偩偟乿傪尒尷偭偨偵偣傛丄帺暘偑偦傟傪夁嫀偺傕偺偵偟傛偆偲偟偨偵偣傛丄偳偭偪傕寢嬊偍傫側偠偙偲側傫偩傠偆丅偦傟偼丄傂偲偮偺娭學偑懝側傢傟傞偭偰偙偲丅傑偀丄偦偆傗偭偰師偵恑傫偱偔傫偱偡偗傟偳傕偹丅枹棃偑偁傞偐傜恖偼惗偒懕偗傞偙偲偑偱偒傞丅偊傜偄僗僂傿乕僩側暥傪曇傫偠傑偭偨側丅僱僢僩儔僕僆偺Xmas僜儞僌傪挳偄偰偨傜丄僀償偵怳傜傟偨婰壇偑傛傒偑偊偭偰偒偰丄偮偄巜愭偑偡傋偭偰偟傑偭偰丅傑偀丄傑傑傛乨  Xmas傁乕偪乕偺婫愡 偁傟偐傜婔擔偑夁偓偨偺偩傠偆丅偍傛偦1100擔偑棳傟偰偄偭偨丄26400帪娫丄158枩4000暘丅帺暘偺拞偵丄側偵偑丄側偵偑丄巆偭偨偺偩傠偆丅 崅3偺嵟婜丄怱偵偁偭偨偺偼丄戝妛偱壗偐傪巆偦偆偲偄偆寛堄丄峝偄恈傒偨偄側傕偺傪偮偐傔傞偲偄偆帺怣丅偁傟偙傟巚偄昤偄偨丅偄傠傫側傕偺傪尒壓偟偰丄僯儎偮偄偰偼丄帺暘偺彨棃偵崨傟崨傟偟偨丅戝妛偼1460擔傪攧偭偰偔傟偨丅庼嬈椏偲堷偒姺偊偵丄帺桼偲愑擟偺帪娫傪偄偨偩偄偨丅戝妛丄偍偦傜偔偦傟偼帪娫傪攧偭偰偔傟傞偲偙傠丅 偁傟偐傜婔擔偑夁偓偨偺偩傠偆丅偍傛偦1100擔偑棳傟偰偄偭偨丅偺偙傝偼丄偍傛偦500擔丄12000帪娫丄72枩暘丅傕偆2乛3偼巊偄壥偨偟偨丅偙傟偐傜壗偑偱偒傞偺偐偼傢偐傜側偄丅偱傕傑偩壌偼怣偠偰傞丅 仴偙偺愘偄暥復偼側傫偩丠偲巚傢傟偨偐傕偟傟傑偣傫丅偱傕丄偄傑丄偲偵偐偔徟偭偰傞丅傑傢傝傪尒搉偣偽丄廇怑妶摦傪偡傞傗偮丄巌朄帋尡偵僩儔僀偟偰傞傗偮丄岞柋堳帋尡偺曌嫮偵椼傫偱傞傗偮丅偡傝尭傞僔儍乕僾儁儞偺恈堦杮堦杮偑彨棃偺惗妶偵捈寢偟偰傞丅傂傞偑偊偭偰帺暘偼偳偆偩傠偆丅堾傪栚巜偡偲偄偆偙偲丅杮堦嶜偑丄偄偭偨偄壗偵偮側偑傞丠尒偊側偄丅傎傫偲偆偵愭偑尒偊側偄丅 乽柌傪幚尰偡傞偵偼偳偆偡傟偽偄偄偐抦偭偰傞偐偄丠乿乗乗乗乗乽栚傪妎傑偡偙偲偝乿 偙傫側廘偡偓傞戜帉偑廳偔偺偟偐偐傞丄偡傋偰偼帺屓娗棟丄帺屓愑擟丄帺暘偺帪娫偺巊偄曽丄偗偠傔偺栤戣丅戝妛偐傜攦偭偨帪娫偺2乛3偼夁偓嫀偭偨丅側偵傕丄偄偐側傞偙偲傕丄傕偆愭墑偽偟偵偼偱偒側偄丅擼攇傪應掕偟側偑傜丄扨挷側攇宍傪儌僯僞乕偵傏傫傗傝偲挱傔側偑傜丄偦傫側偙偲傪峫偊偨丅偄傗丄杮摉偵偙傟偑偡傋偰丅 帠審偵偮偄偰 徚偝傟偨彈偺HP偺儈儔乕僒僀僩 偁偲偱備偭偔傝栚傪捠偟偰傒傛偆偲巚偆丅 仱傕偆偡偖僴儘僂傿儞偩丅偨偄偰偄偺恖偼寉偔棳偡偑丄峫偊傛偆偵傛偭偰偼偙傟傎偳柺敀偄僀儀儞僩傕側偄丅扤傕偑側偵偐晛抜偺帺暘埲奜偺傕偺傪墘偠傞偙偲偑嫋偝傟偨堦擔偩偐傜丅偐傏偪傖偼丄帺暘偐傜偺夝曻偺徾挜揑僔儞儃儖偵尒偊偰偔傞丅側偵傕嬅偭偨堖憰傪攦偆昁梫側傫偐側偄丅愄偺惂暈傪庢傝弌偟偨傝丄晛抜拝側偄僗乕僣傪拝偰丄晛抜峴偐側偄偲偙傠傊峴偭偰傒偨傝偡傞丅偦傟偱丄側偵偐堖憰偵墳偠偨栶傪墘偠愗偭偰傒傟偽妝偟偄丅婥傑偢偔抦傝崌偄偵弌夛偭偰傕丄乽僴儘僂傿儞偩偐傜!乿偺僸僩僐僩偱嵪傓丅偦偆丄僴儘僂傿儞偲偼曄恎婅朷偺柶嵾晞側偺偱偟偨丅僶僀僩愭偱偼傗傟儈僯僗僇億儕僗偩娕岇晈偩丄偭偰乨儔僽儂偱傗傟傛揑側婅朷偺堦斒岞奐偑嫋偝傟傞偙偲傊偺僼傿乕僶乕丅偦傫側帺暘偼丄偝偰偝偰乨 仴乽抦揑愥偐偒乿偲偄偆尵梩丅偨偟偐懞忋弔庽偺彫愢偺偳偭偐偵弌偰偒偨偲巚偆傫偩偗偳丄嵟嬤偺帺暘偵偡偛偔偟偭偔傝偲偔傞丅悽偺拞丄帺暘偵偲偭偰堄枴偑偁傞偲姶偠傜傟傞偙偲偽偐傝傗偭偰偄傟偽椙偄傢偗偱偼側偄丅偨偲偊偽妛惗偲偟偰丄懖嬈偺偨傔偵丄傗傝偨偔側偄丒嫽枴偺傕偰側偄東栿傗壽戣傪偙側偝側偗傟偽側傜側偄丅帺暘偵偲偭偰偼丄怱棟妛偺帇妎傗擼偵娭偡傞嵶偐偄尋媶榑暥偺島撉僾儗僛儞僥乕僔儑儞偩偭偨傝丅乽抦揑亖摢傪巊偭偨乿乽愥偐偒亖攏幁傜偟偄傎偳偺搆楯偩偗偳丄慜偵恑傓偨傔偵偳偐偝側偒傖偄偗側偄傕偺傪偳偐偡嶌嬈乿丅億僀儞僩偼丄偳偐偟偰傕丄偳偐偟偰傕丄師偐傜師傊偲崀傝愊傕偭偰偒偰丄偦傟偵朲嶦偝傟傞偲偄偆偙偲乗乗愥偐偒偺懱椡傪拁偊偲偗偽屻乆栶偵棫偮偙偲傕偁傞偩傠偆偲怣偠偰丅 |