・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
「グローバリゼーション」の輪郭線part.1
 「グローバリゼーション」という語がキーワードになったのは、1996年の主要国首脳会議(リヨン・サミット)からだと言われる。「暴走する世界」が生み出す当惑と不安を象徴的に示す、多義的な言葉なのだろう。これまで専門的な文献を追ったことがなかったため、一初心者として、読んだものをメモし、輪郭線を僅かばかりでもはっきりさせてみたい。素人の方には、何らかの参考になるかとも思う。
「グローバリゼーション」という語がキーワードになったのは、1996年の主要国首脳会議(リヨン・サミット)からだと言われる。「暴走する世界」が生み出す当惑と不安を象徴的に示す、多義的な言葉なのだろう。これまで専門的な文献を追ったことがなかったため、一初心者として、読んだものをメモし、輪郭線を僅かばかりでもはっきりさせてみたい。素人の方には、何らかの参考になるかとも思う。
資本の移動と人の移動(=移民)、これらは国民国家がコントロールしきれない二つの大きな課題だ。先進国はここ数十年間、市場主義にもとづき、資本・もの・情報などの国境を越えた自由な移動を推進してきた。ところが、人間(労働力商品)の流入は可能な限り統制され制限されてきた。モノのフローは奨励される。でも人のフローは当惑される。さて、このことを念頭において、第1回目は、今日のグローバリゼーション研究の理論的枠組みを提示したといわれるサスキア・サッセンの思索を見ていこう。「グローバリゼーション」の経済的側面について。主にアメリカについての分析。
先進国の製造業は、本国における高い労働コストと厳しい規制を逃れるために、生産拠点を途上国に移転するようになった。途上国の政府もまた免税特権などで企業誘致につとめてきた。移転した企業は、現地市場向けの完成品を生産するのではなく、本国から部品を輸入し、それを加工した後に輸出する、オフ・ショア生産を行う。こうして現地工場は、資本投資国を頂点とする生産ネットワークに組み込まれていく。
現地の工場で生じた労働需要は、農村社会から若年労働力を吸い上げることによってまかなわれた。労働力を失った農村社会の生活は危機に陥った。また、現地工場では主として若年女性が雇用され、男性労働者の大量失業が生じたが、企業が海外生産拠点(工場)を移転する度に、雇用されていた女性労働者も失業した。こうして生産のグローバル化に伴って、途上国の内部に膨大な移民予備軍が累積されていった。重要なのは、先進国企業が途上国に展開する際、(先進国で享受されている)大量消費的な文化や生活様式を浸透させていったということだ。消費生活に一度慣れてしまえば、もう後戻りはできない。したがって、途上国の中心都市に、「もはや帰るべき故郷をもたない」失業者が大量に生じ、移民の潜在的予備軍となった。
以上が途上国におけるプッシュ(押し出し)要因だが、サッセンの洞察は、先進国側の移民を引きつけるプル(吸引)要因を見いだしたことにあった。企業の生産部門は海外に移転したが、他方で、(IT技術の飛躍的発展もあり)多国籍化した企業の管理中枢や金融部門は特定の大都市に集中していった。この特定の大都市を「世界都市(global city)」とサッセンは名付けた。「世界都市」では、従来型の産業構造の主役であった中所得層のホワイトカラーとブルーカラーが減少し、高収入を得る専門的技能職従事者と、サービス業や製造業に従事する膨大な低賃金労働者とに分化していった。「世界都市」はビルの清掃・管理などに従事する膨大なサービス労働者に対する需要を生み出し、また高所得者層の増大は、家政婦、ベビーシッター、商品の配送など多種多様なサービス労働への需要を生み出した。これら底辺の職種に、先進国の労働者はなかなかつきたがらない。これを担ったのが移民労働者たちであった。無権利で従順な移民労働者によってしか充たされないような低賃金労働に対する需要が、大量の移民を先進国に引きつけた、プル(吸引)要因であった。
アメリカでは1960年代に公民権運動や女性解放運動などが発展した結果として、従来底辺労働力を構成していた、黒人や諸マイノリティ集団、女性などの社会的地位や所得が上昇した。この結果、家事、育児をはじめとする家庭内サービス労働に対する膨大な需要が生まれ、この需要に応えたのは(不法な)移民女性たちだった。こうして同一ジェンダー内部のグローバルな格差構造が作られていった。
先進国は両義的な役割を果たしてきたといえる。一方で金融・生産・輸出入の自由化を途上国に要求し、他方で移民の流入に関しては厳格な規制と管理を行ってきたのだ。もちろん現実的には、先進国の内部に移民労働に対する需要が存在する以上、政府の規制をかいくぐって「不法に」流入する入国者の流れを阻止するのは難しい。注意すべきは、政府が国境を管理することによって入国者に刻印される「合法移民」「不法移民」という烙印があればこそ、経営者はかれらを先進国本国の労働者よりも劣悪な労働条件、安い給与水準によって働かせることができ、かつ人権を侵害する不当な待遇に対する外国人労働者の抵抗を封じることができたということだ。先進国は途上国に移民予備軍を作り、また先進国内部に移民を引き寄せるプル要因を作ったのだが、移民流入は制限することによって、移民の劣悪な労働条件を正当化してきたのだ。国家は国内における移民の差別化の機構として、資本の利害と共犯関係にある。
もっとも、先進国の底辺労働に従事している移民労働者は、移民するすべすら持たない故郷の労働者よりは恵まれた地位にあるといえる。現代における移民現象は、グローバルな労働力移動の性格を持っている。第1に、あらゆる途上国内部で生じている農村から都市へ向かう人口移動を底流としつつ、第2に、途上国内部における低所得地域から高所得地域への移動(たとえば貧しい中東諸国から豊かな石油産出国への移民流入)が世界各地域で展開していることを背景として、第3に、それらの最上層に途上国から先進国へと向かう移民の流れが存在するのだ。南北という単純な二分法はもはや通用しない。
資本主義のグローバルな展開に規定された労働力のグローバルな移動と格差の構造を考えると、国民国家の法制度に依拠した支援策の限界が明らかになる。では、どうすれば良いのか。この事態をどのように考えてゆけばよいのか。それについてのメモは、またの機会に。なお、上記は『グローバリゼーションとは何か』、『グローバリゼーションの時代』に詳しいが、基本的に『哲学』第55号pp.4-19「グローバリゼーションという現実」(平子友長)を参考にメモさせていただいた。筆者独自の論考は含まれていない。


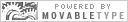
***→