・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
株をめぐる言説の整理
 ホリエモンや日銀福井総裁や村上世彰氏に対するバッシングは常軌を逸して凄まじかったが、一部のバッシングの基底には、『「マジメに働かず」株(ファンドへの投資)によって儲けるなんて許せねー』的な嫌悪感が見え隠れしていた。株やってる人間ってどーなのよ。
ホリエモンや日銀福井総裁や村上世彰氏に対するバッシングは常軌を逸して凄まじかったが、一部のバッシングの基底には、『「マジメに働かず」株(ファンドへの投資)によって儲けるなんて許せねー』的な嫌悪感が見え隠れしていた。株やってる人間ってどーなのよ。
さて、株取引(に絞って話をするが)をやっている人間は、この「おまえら社会的にろくでもないことしやがって」という批判に対して、大まかに3点から反論する傾向があると思う。以下に詳しく述べていくが、第1の反論は、株式投資という仕組みの社会的意義を説く。第2の反論は、株式投資のあるべき姿を説く。そして第3の反論は、たとえデイトレードであれ、株式投資という行為そのものが無条件に社会に貢献するのだと説く。
第1の反論は、株式投資こそが唯一大きなプラスサムの価値創造を推進する手段だ、というもの。経済を発展させるためには、不確実な(成功するかどうかわからない)事業を立ち上げ、それに誰かが投資することが不可欠だ。冒険無くしては大きなブレークスルーが生まれないからだ。その不確実な事業に対して、多くの人が株式投資を行うことによって、元本割れリスク(不確実性)の引き受け手を広く社会に分散させることができる。この観点からは、株取引を行う人たちが、無条件に肯定されるといえるだろう。なぜなら、彼(女)らは、経済発展のためのリスクを引き受けた、勇敢な戦士たちなのだから。
「資本主義の最大の強みは、普通株という有限責任の投資対象を通じて、国民が全員参加してリスクを分担し、結果の保証されない新しい経済活動を支援するところにある。わが国では資金調達といえば銀行借り入れを、資金運用といえば預金や国債、保険や年金などの確定利付き商品を思い浮かべる。古今東西、国家主導経済においては銀行中心の確定利付き型金融システムが主流であり、日本はその代表的な国であったから、それも無理からぬことである。これに対して、リスクを取る行為を組織的に支えるために、普通株という有限なリスクの投資対象を広く国民の間に分散して持ってもらうという考え方は、大航海時代から18世紀イギリスの産業革命を契機とする、資本主義経済に固有の一大発明なのである。結果のわかっているローリスク事業、あるいは結果の保証されているノーリスク事業なら、銀行借り入れや財政資金によっても推進することは可能であろう。しかし、結果が不確実な新しい事業の推進は、まずリスク資本が調達され、投入されるところから価値創造が始まるのである。(『証券投資入門』)
第2の反論は、「株式市場は、価値創造の担い手である企業のパフォーマンスに最終的な評価を下す、資本主義経済の最高裁判所だから必要なんだぜ」というもの。株取引を行うことは「最高裁判所」で裁くことに似ているというこの主張は、当然のことながら、株取引に規範(裁き方のルール)が必要なことを説く。株式は、国民の大切なリスク資本の活用をプロの経営者に委ねることを通じて、リスクを全員で負担しつつプラスサムの経済的価値の創出を推進することを目的としていたが、その目的を達成できるかどうかは、(1)株主の利益に奉仕する経営者が率いる企業と、(2)企業のパフォーマンスを適切にモニタリングし、株価によって評価する投資家(裁判官)という、2つのグループの共同作業に依存している。投資家が企業の業績を適切に評価して正しく株価水準を設定できなければ、企業や産業に資源や資本がふさわしくない条件で再配分され、ひいては国民全体の大きな経済的損失につながる、というわけだ。株をやる人間は資本主義の裁判官という役割を担っており、それゆえに自分たちが企業を育てているのだという自覚を持ち、規範(株価によって企業の業績を適切に評価し企業を育てろという命令)に従え、というわけだ。
この観点からは、株取引を行う人たちが、条件付きで肯定されるといえるだろう。決算書を読み、現代投資理論に基づいて適性株価水準を推測し、割安株を買い割高株を売る(つまりはファンダメンタル分析をきちっと行う)者たちは肯定される。企業を成長に導く投資を心がける者は受容される。中・長期的投資が好ましいとされる。他方、短期投資(デイトレード)を行う人などは、株価を乱高下させる悪者とされる。投資は善、投機はは悪とされる。
第3の反論は、株取引という行為そのものを、そして何よりもデイトレードなどの投機行為そのものを根本から肯定する。「俺たちは株を頻繁に売ったり買ったりすることによって市場に流動性を提供しているんだ。あなたが株を売りたいときに売れない、買いたいときに買えない、じゃ困るだろ?市場に流動性を確保することによって、経済学的な意味で、効率性が担保され、経済発展に貢献しているんだ」というもの。この観点からは、デイトレーダーを含め、あらゆる株取引を行う人たちが肯定されるだろう。たとえば、株ではないが為替市場について、『生き残りのディーリング』の著者、矢口新はこう述べる。
では、市場から投機筋を一掃すればどうなるか論じてみましょう。為替市場を例にすると、市場での取引は、財・サービスの輸出入に絡む実需と、旅行者などの外貨、邦貨の手当、資産の裏付けのある投資とその収益の送金などに限られてしまうでしょう。出来高は今の数パーセントとなり、売りたい人は買いたい人が現れるまで待ち続けねばなりません。(中略)日本のように貿易が大幅黒字の国では、外貨を売りたい人が行列を作って、買い手を待つことになります。しかも、この行列は日増しに長くなるのです。(中略)売れない市場に買いを入れる投資家はいません。投資家がもっとも恐れるのは、流動性の欠如だからです。(中略)このように、投機筋の市場における役割は非常に大きいのです。投機筋あっての市場ともいえるでしょう。誰かがリスクを取り、踏みこたえることによって、実需の偏りの緩衝材となり、過度の変動を押さえるのです。」
以上、株取引を擁護する代表的な3つの言説を見てきたのだが、どうだろうか。長期投資家は三位一体の王国に君臨しているため、批判を受けにくい。他方、デイトレーダーは、株式投資の「規範性」(第2の反論)を蔑ろにしていると考えられるため、批判の矢面に立ちやすい。「株をやっている人間、ましてや大儲けしている人間は嫌い」と感じるのは自由だが、彼(女)らを批判する場合、何に対して嫌悪感を抱いているのか、改めて自己の意見の内実を整理する必要があるように思う。彼(女)らは、資本主義の枠内では、まぎれもなく社会的な貢献をし、公共性に資している。彼らが大儲けしたのは、その分リスクを引き受けたからだ。1億円儲けるかわりに、1億円の資産を失う、あるいは1億円の借金を背負うリスクを黙諾していたのだ。竹原慎二のボコボコ相談室が宣うがごとく。汗水垂らして働いた資金を失う、あるいは借金を背負うリスクを引き受けた分だけ儲けたのであり、その意味で株取引は、自らの労働そのものを賭ける行為といえるだろう。彼(女)らを批判する契機が存在するとすれば、それは脱資本主義的な言説の中にしか存在しえないだろう。マルクス的な、資本の自己増殖性を糾弾する視座以外に、どのような言説がありうるのだろうか。
#現代投資理論関係のおすすめ書籍をいくつか紹介します。まず、『証券投資論』は投資アナリスト試験のバイブルと呼ばれ広く親しまれていますが、少し難解なので、初心者には『証券投資入門』をおすすめします。また、現代投資理論の根底にあるファイナンスを難しい数式抜きに明快に理解させてくれる好著として、『道具としてのファイナンス』は絶対的にお勧め。最後に、企業の決算書を読むための基礎を身につける本として、『MBA財務会計』はきわめて明快に論じてある快著。本当にわかりやすいので、ぜひ。


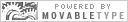
***→