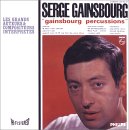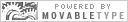・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
July 28, 2006
株をめぐる言説の整理
 ホリエモンや日銀福井総裁や村上世彰氏に対するバッシングは常軌を逸して凄まじかったが、一部のバッシングの基底には、『「マジメに働かず」株(ファンドへの投資)によって儲けるなんて許せねー』的な嫌悪感が見え隠れしていた。株やってる人間ってどーなのよ。
ホリエモンや日銀福井総裁や村上世彰氏に対するバッシングは常軌を逸して凄まじかったが、一部のバッシングの基底には、『「マジメに働かず」株(ファンドへの投資)によって儲けるなんて許せねー』的な嫌悪感が見え隠れしていた。株やってる人間ってどーなのよ。
January 17, 2006
「グローバリゼーション」の輪郭線part.1
 「グローバリゼーション」という語がキーワードになったのは、1996年の主要国首脳会議(リヨン・サミット)からだと言われる。「暴走する世界」が生み出す当惑と不安を象徴的に示す、多義的な言葉なのだろう。これまで専門的な文献を追ったことがなかったため、一初心者として、読んだものをメモし、輪郭線を僅かばかりでもはっきりさせてみたい。素人の方には、何らかの参考になるかとも思う。
「グローバリゼーション」という語がキーワードになったのは、1996年の主要国首脳会議(リヨン・サミット)からだと言われる。「暴走する世界」が生み出す当惑と不安を象徴的に示す、多義的な言葉なのだろう。これまで専門的な文献を追ったことがなかったため、一初心者として、読んだものをメモし、輪郭線を僅かばかりでもはっきりさせてみたい。素人の方には、何らかの参考になるかとも思う。
December 29, 2005
信頼についてpart.1
 卒論に関連して、リスクに関する意識調査の質問紙を大量にばらまいた。感想欄に寄せられたコメントの多くは、「誰を(どの意見を)信用すればよいのか分からない」と訴えかけていた。信じること、ないし信頼。この信頼の重要性は、専門分化した現代社会において、なおさら重要だといえよう。本日は、信頼に関する心理学的知見を軽く概観してみたい。あなたが日常生活で信用を勝ち取るためのヒントも詰まっているはず。
卒論に関連して、リスクに関する意識調査の質問紙を大量にばらまいた。感想欄に寄せられたコメントの多くは、「誰を(どの意見を)信用すればよいのか分からない」と訴えかけていた。信じること、ないし信頼。この信頼の重要性は、専門分化した現代社会において、なおさら重要だといえよう。本日は、信頼に関する心理学的知見を軽く概観してみたい。あなたが日常生活で信用を勝ち取るためのヒントも詰まっているはず。
December 23, 2005
自然保護運動への嫌悪感、を越えて
 お久しぶりです。長いあいだ音信不通でご迷惑をおかけした関係者各位には、これから説明に伺う予定です。すみません。ところで、「地球にやさしい」というキャッチコピーや、そのおおもとであるところの自然保護運動に対して、何かしらのうさんくささを感じませんか。自分もその一人でした。うさんくささや若干の嫌悪感を感じ続けてきた。でもつい先日、自分なりにその嫌悪感と折り合いを付ける道を発見したので、メモしておこうと思います。
お久しぶりです。長いあいだ音信不通でご迷惑をおかけした関係者各位には、これから説明に伺う予定です。すみません。ところで、「地球にやさしい」というキャッチコピーや、そのおおもとであるところの自然保護運動に対して、何かしらのうさんくささを感じませんか。自分もその一人でした。うさんくささや若干の嫌悪感を感じ続けてきた。でもつい先日、自分なりにその嫌悪感と折り合いを付ける道を発見したので、メモしておこうと思います。
July 23, 2005
パリの建築と景観、そして移民
 パリの建築について軽く調べていた。パリは建てるにも壊すにも規制が厳しすぎる。だからあれだけの街の雰囲気が残存しているわけでもある(ちなみに昨今は住居不足によるバブル気味だそうで、マンション一室の値段が購入時と比べて2倍にアップした例などはザラだとか)。地震は来ないので、耐震性は問題とならない。その点対照的な「京都の街並み保存計画」は興味深いけれども、また別の機会に。
パリの建築について軽く調べていた。パリは建てるにも壊すにも規制が厳しすぎる。だからあれだけの街の雰囲気が残存しているわけでもある(ちなみに昨今は住居不足によるバブル気味だそうで、マンション一室の値段が購入時と比べて2倍にアップした例などはザラだとか)。地震は来ないので、耐震性は問題とならない。その点対照的な「京都の街並み保存計画」は興味深いけれども、また別の機会に。
April 28, 2005
April 26, 2005
外見を気にする人間は「チャラい」?
 本家サイトのGuestbookにて、「僕のように髪型などの容姿の事でクヨクヨ悩む事ってありますか?これってバカバカしいことですか?」と質問を投げかけられた。自分にも無縁じゃないので、一度きちんと考えてみよう。人生論や「ナルシスト」論とも関わってくるだろう。
本家サイトのGuestbookにて、「僕のように髪型などの容姿の事でクヨクヨ悩む事ってありますか?これってバカバカしいことですか?」と質問を投げかけられた。自分にも無縁じゃないので、一度きちんと考えてみよう。人生論や「ナルシスト」論とも関わってくるだろう。
January 24, 2005
性善説か性悪説か
 人間は性善なのか、あるいは性悪なのか、かくも結論無き問題が長々と語られてきた。この問題を人間のnatureとして考え、科学の名を騙るならば、進化論から考察するのが妥当だろう。さて、あなたはどちらが正しいと考えていますか?
人間は性善なのか、あるいは性悪なのか、かくも結論無き問題が長々と語られてきた。この問題を人間のnatureとして考え、科学の名を騙るならば、進化論から考察するのが妥当だろう。さて、あなたはどちらが正しいと考えていますか?
January 21, 2005
感情の進化論3――感情は学習の教師である
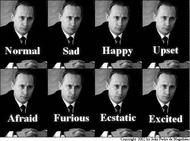 前回書いたように、感情が理性の根底に横たわっている。感情はこの世に意味を与え給う神である。では、生まれつき授けられた感情によって、人間は盲目的・自動的に導かれるのだろうか?ちょっと待った。「学習」と「推論」という極めて重要な問題がまだ残されている。それは「遺伝」の反対側に位置する、「環境」の問題でもある。いよいよ感情、学習、推論のしっぽりとした関係にガサ入れしていきます。
前回書いたように、感情が理性の根底に横たわっている。感情はこの世に意味を与え給う神である。では、生まれつき授けられた感情によって、人間は盲目的・自動的に導かれるのだろうか?ちょっと待った。「学習」と「推論」という極めて重要な問題がまだ残されている。それは「遺伝」の反対側に位置する、「環境」の問題でもある。いよいよ感情、学習、推論のしっぽりとした関係にガサ入れしていきます。
その前に一休憩。グラサンかけてないタモさんの画像はなぜか申し訳ない気持ちを喚起し、タモリ発言200選で時間を素敵に食い潰し、某英単語の意味がここ1ヶ月で変わったという記事に鼻を鳴らし、およそ百年前に撮影された写真に涙を流し、プーチンに背筋を凍らし(右上の写真をclick)、さてと行きますか。
続きを読む...January 18, 2005
感情の進化論2――感情無しに意味は存在しない
 Imagine. 想像してみて欲しい。感情無き世界を。あなたは生きるだろうか。死ぬだろうか。指さすだろうか。空を仰ぎ見るだろうか。何かに判断を下すだろうか。否、微動だにしないだろう。思考は停止するだろう。そこは「〜したいと欲する」ことが一切無き地平。点滴をつながれているならば、アメーバやロボットのように生きながらえるだろう。その時あなたはもしかしたら認知科学者に諸手を挙げて迎え入れられるのかもしれない。なぜならあなたは、純粋なコンピュータ的自動装置と化したのだから。
Imagine. 想像してみて欲しい。感情無き世界を。あなたは生きるだろうか。死ぬだろうか。指さすだろうか。空を仰ぎ見るだろうか。何かに判断を下すだろうか。否、微動だにしないだろう。思考は停止するだろう。そこは「〜したいと欲する」ことが一切無き地平。点滴をつながれているならば、アメーバやロボットのように生きながらえるだろう。その時あなたはもしかしたら認知科学者に諸手を挙げて迎え入れられるのかもしれない。なぜならあなたは、純粋なコンピュータ的自動装置と化したのだから。
快・不快の感情は人間を動かす根本的なエネルギー源である。感情機構は、出来事という外的事象や空腹といった内的事象、つまり燃料を動力に変えるモーターだ。あなたが「人間」であるのは、感情を忍ばせているからなのだ。感情は意味の世界を創造する「神」なのかもしれない。
続きを読む...January 17, 2005
感情の進化論1――世界は幻想である
 友人のBlogで玉音放送の現代語訳を読み想いを新たにしたせわしない今宵、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、感情の進化論。またの名を、「この世界」の科学論。根源的な哲学でもある。重要なテーマなのでシリーズ化してわかりやすく書きます。長いですが、マジで面白いですよ。(註:わたしは進化的機能主義の立場から書いています。異論のある方はコメント欄に遠慮なくどうぞ)
友人のBlogで玉音放送の現代語訳を読み想いを新たにしたせわしない今宵、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、感情の進化論。またの名を、「この世界」の科学論。根源的な哲学でもある。重要なテーマなのでシリーズ化してわかりやすく書きます。長いですが、マジで面白いですよ。(註:わたしは進化的機能主義の立場から書いています。異論のある方はコメント欄に遠慮なくどうぞ)
May 28, 2004
「日本人らしさ」は存在するのか?Vol.1 文化心理学を通じて
 私たちはよく「その考え方っていかにも日本人的だよな」「日本人って集団主義的だから俺には合わないんだよな」などと口にする。だがそもそも「日本人らしさ」って、一体何だ?以前のエントリーと重複しますが、丁寧に論じてみました。日本人は欧米人より集団に流されやすく、日本は村社会的だと感じてしまう人は、是非一度読んでみてください。
私たちはよく「その考え方っていかにも日本人的だよな」「日本人って集団主義的だから俺には合わないんだよな」などと口にする。だがそもそも「日本人らしさ」って、一体何だ?以前のエントリーと重複しますが、丁寧に論じてみました。日本人は欧米人より集団に流されやすく、日本は村社会的だと感じてしまう人は、是非一度読んでみてください。
一番普及している考え方は、西欧人は「個が確立しており、自己主張が強く、人の意見に流されにくい」、それに対し日本人は「個よりも和を尊び、集団主義的で、人に流されやすい」というものだろう。この考え方に沿って様々な書物が著されてきた。たとえばルース・ベネディクトの『菊と刀』が代表例だろう。またこの考え方は受験現代文・小論文の現場でも絶えず繰り返されており、学生を通じていまだに反復/再生産され続けている。
この文化による考え方の違いを、「文化による心性の違い」と捉え、心理学の領域で扱うことも可能になる(文化心理学)。日本で代表的なものとしては、京大の北山忍(とその一派)によるものがある。彼は、これまでの心理学は文化差による心性の違いを無視し、「個」としての心性を重視しすぎていたと批判する(これまでは心性単一性を仮定していたが、心性の潜在的多様性を仮定すべし!と)。彼によると、
「心理プロセスは文化の内容をなかに取り込むことにより成立し、それらに囲まれることにより維持され、同時に、文化の内容は心のプロセスの活動そのものを映し出している。つまり、心と文化は歴史的循環のなかで互いに生成しあうものである。(中略)この意味において、文化は実質的に心を作り上げており、また同時に、文化そのものも多くの心がより集まって働くことによって維持・変容されていく」(『文化心理学』)続きを読む...
April 28, 2004
集団先鋭化の論理&Blogは議論に不適?
 右翼にしろ左翼にしろ、ひとたび集団がある方向に動き出すと、その集団の方向性はかならず先鋭化する。逆方向へ戻すような意見は、日和見主義として軽んじられ、過激な意見が通りやすい集団力学が働く。この際集団を構成する者の頭がいいとか悪いとかは関係ない。戦時中の軍部の暴走も同様のロジックによって語りうる。何事かをはじめるのは簡単だ。しかし止めるのは、困難を極める。
右翼にしろ左翼にしろ、ひとたび集団がある方向に動き出すと、その集団の方向性はかならず先鋭化する。逆方向へ戻すような意見は、日和見主義として軽んじられ、過激な意見が通りやすい集団力学が働く。この際集団を構成する者の頭がいいとか悪いとかは関係ない。戦時中の軍部の暴走も同様のロジックによって語りうる。何事かをはじめるのは簡単だ。しかし止めるのは、困難を極める。
大いなる思考は会議で生まれた事はなかったが、馬鹿な多くの考え方もそこで死滅した(フィッツジェラルド)。
常に現実の動きに注意を払いつつ、早め早めにアクションを起こしていくことが、肝要なのだろう。Blogの意義があるとすれば、それはフィッツジェラルドがいうような意味においてではないか。ただ、Blogでは会議にはならない。Blogはあくまで個人の一軒家であって、居酒屋でも会議室でもない。ただの日記が電話の通じない家だとすれば、トラックバックは電報が通じるようになったにすぎない。訪問は果てしなく面倒くさい。会議をするならBBSだ。それでもBlogは、「馬鹿な多くの考え方」を死滅させることくらいはできるようにも思う。早め早めに。
あるいはもしかしたら、「偉大な思考」が生まれる場かもしれない。もしかしたら。
April 27, 2004
焦燥感
本格的に大学院のゼミで議論したり、自分が進学を考えている院のHPを見ていて、果てしない焦燥感に襲われたので、しばらくは寸分を惜しんで読書に没頭します。更新頻度は落ちたりあるいは数日後にはまたケロッと書いているかもしれませんが、気が向いたらまた訪れてやってください。
余談。自分は<いかに対象にアプローチするか>という方法論的な関心が非常に強いんですが、実際に<何を対象として接近したいのか>という観点が非常に希薄なことにあらためて気づいてしまった。何を知りたいのか、何を解き明かしたいのか、何に触れたいのか、そう問われたときに曖昧な空白がほげーっと姿を晒けだす。さらに卒論を心理学と文化人類学のインターフェースで書き上げようと思っている上に、哲学・社会学・進化論の基礎知識の不備を補わなきゃ気がすまないので、破綻しそう。あーせっかくデリダのポジシオンを手に取り始めたのに。
いくら留年しようともあと2年弱しかないことに愕然としました。院試までだと600日程度か‥研究計画書が書けない。テーマ絞り込めない。微細な領域内の先行研究から、演繹的に研究テーマを設定する、心理学固有のやりかたに理性が従属してしまっていた。目的意識が先鋭化すればするほど、広がるものが膨大すぎて、にっちもさっちもどこにも行けない。なお個人的な読書日記とメモは、はてなダイアリーにつけてゆくつもりです。金時鐘の詩が痛い。(『地平線』)
行きつけないところに 地平があるのではない.
おまえの立っている その地点が地平だ.
April 24, 2004
人間と動物の「乱交文化」
『心の進化―人間性の起源をもとめて』冒頭の座談会より興味深かったものをいくつかメモ。
松沢(霊長類研究者):例えば、チンパンジーやゴリラには、アドレッセンス・ステライル(思春期不妊)という現象があるんです。思春期に交尾はするけれども避妊はしない時期がチンパンジーでもゴリラのメスでも2年くらいあります。この時期のゴリラは非常に乱交的になり、いろんな集団を渡り歩いて、いろんなオスと交尾するということがおこる。
船曳(文化人類学者):マリノフスキーの『トロブリアンド諸島』の研究にあるのですが、初潮以降に女の子と男の子たちが一種の乱交状態に入るんです。それが数年続く。子供が生まれないんですよ。やっぱりそのある時期を通り越して、そして今度は本当の大人になるという。だから僕は、人間が作り上げたいろいろな機能、細かなルールなどのために簡単には出てこないのだけれども、ときどきプツップツッと自然が噴き出すときがあると思っていて、それが例えば今の高校生の性に対するある感じや、日本人の避妊に対する態度とか、いろんなことに顕れていると思うんですね。
何事も「他のものと比較する」という行為を抜きにしては、探求したいものの特質を同定することはできない。過去との対比が「歴史」と「現代」を作った。異なる地域の人間との比較が、「文化」を創造した。あるいは、他人の考えを知ることによって、はじめて「自分」とはなんたるかをおぼろげながらに知ることができる。そして、「人間と、人間でないものを比較する」という営みは、さらなる次元を切り開き続けるように思われる。その意味で、進化論的な話はあまりに魅力的過ぎる。人文系の思想的・理論的な流れと、進化的知見の融合/反発は、絶対に探求し続けねばならないテーマなのだろう。両方への目配りを。船曳さんのいう「プツップツッ」を何とか構造化して説明できないものだろうか。

船曳:イギリス人の男に「子供と奥さんどちらかを助けなければいけない、という状況に陥ったとしたらどちらを助けるか」という質問をすれば「妻」と答え、女の人に聞けば「夫」と答えざるを得ないのだが、日本ではほとんど「子供」という。つまり、愛という形が日本とイギリスではぜんぜん違うといのです。(中略)
松沢:でも90年代、われわれ霊長類学者はチンパンジーがシロアリ釣りをするなんて乱暴なことはいわない。チンパンジーは確かにシロアリ釣りをするけど、それはゴンベ(地名)のチンパンジーがシロアリ釣りをするんであって、私が見ているギニアのチンパンジーは、シロアリをつまんで食べるけどシロアリ釣りはしないと。
船曳:文化人類学と一緒ですね。(種の内部の)文化の違いをいうわけだ。
松沢:文化と張りついた自然性という、種のレベルで決まっているわけではなくて、その種がいろいろな環境に適応していく中であらわれてくるもの。(中略)土地、風土、森、そこの食物生産量、そういったものがいかに社会を規定しているのか、これを読み解きたい。
動物にすら、同種でもそれぞれの生態的環境に応じた異なる「文化」が存在するという、明白な証拠の数々。人間が便利だから曖昧なまま用いてきた「文化」という概念は、人間以外の種が持つ「文化」というものと比較されることによって、より解体されていくのだろう。それは生態系へどんどん拡散していくようにも思われる(ex.マーヴィン・ハリス)。その上で、人間をとりまく「意味の世界」を考えたとき、いったい何が見えてくるのだろうか。
April 23, 2004
ロス暴動と「対テロ戦争」
ロス暴動の際のある地域社会運動家のことば。(ジュディス・L・ハーマン『心的外傷と回復』より)
そう、「正義」も「平和」もあるものか。
きみなら、そりゃまあそうさというかも。
だけど、私には、けっこうひどい、いや、うーむ、
むつかしいことじゃない。ずしーんと深いというか、
浅くはないな、どこもかしこも。
ほんとのほんとはこうだ。正義がここにないなら
やつらに平和をくれてやらない。
きみも知ってのとおり、私たちに平和がない。
奴らも平和がなくなるさ。
この感覚って、自分も抱いたことがあります。たとえば身近なものとして学校/教師の圧倒的な権力的暴力に接したとき、これに似た感情を抱きませんでしたか?もう何をしようとどうでもよくなる感覚。イスラエルによる圧倒的なパレスチナへの権力的暴力。そしてアメリカ政府が遂行している「対テロ戦争」。前に紹介したIraq Body Countによれば、現時点で死者の累計数がmaximum10769人に達しています。目の前で圧倒的な権力の暴力に触れたとき。あるいは、圧倒的な権力の暴力で愛する者が虐げられた様を目撃したとき。――「対テロ戦争」が行き着く先は、どこにあるのでしょう。
April 22, 2004
『必読書150』
イラクの歴史とか民間活動についてとか書きたいことは山ほどあるのですが、さすがに週末にまわします。さて、柄谷行人とか浅田彰といったまぁそっち系の方々が集まって書いた『必読書150』という本があります。キャッチコピーは「これを読まなければサルである」と挑発的。で、偶然にもその読書リストで何があげられているかを掲載しているBlogを発見(shuのつれづれなるままにさん)。あなたはどれくらい読みましたか?
必読書150
柄谷 行人, 岡崎 乾二郎, 島田 雅彦, 渡部 直己, 浅田 彰, 奥泉 光, スガ 秀実
ひとこと。ここに挙げられている本は、日常世界を根底から動揺させる意欲と強さに満ちた珠玉のテクストだとは思うけれども、その種の教養は好きな人がまとえば良いのであって、オルタナティブな教養も確実にあるし、まずそれが重要だと思う。どうしても職人さんが頭の隅から離れなくて。でも、この150冊で考えたものを自分の身体感覚と統合させられれば深い人間になれるはず(4年以内に全部読もう)。またとにかく、「無知の知」「不可知の知」をもたらしてくれるという意味では、素晴らしい。以下、参考までに。
The Consolation of Philosophy: No. 6「この世界において、自分にはわからないことは何もない」とついつい言いたくなりますが、人間に確実に知ることのできることとそうでないことを区別し、人間にとって重要な事柄から優先して知るようにしようという謙虚かつ実用的な態度は、われわれの日常生活でも重要ですし、現代科学に何ができるかという問いについて考えるときにも重要になってくると思います。「知らないことを知っている」というソクラテス流の「無知の知」と同様に、「何を知ることができないかを知っている」というロック流のいわば「不可知の知」もわれわれが生きる上で大切な知見だと言えるでしょう。
April 19, 2004
今学んでいるものを淡々と書いてみるよ
イラクをひとまず離れて個人的エントリーです。大学生が何学んでるのか興味ある人も数人はいるだろう、ということで、自分がどういう授業をこの夏学期に取っているのかを紹介してみようという企画です。興味ないならばスルーが吉です。文系は楽、とかいったのは誰ですか?
続きを読む...April 09, 2004
ついに大学院を絞り、留年を決意。
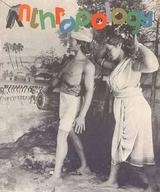 これは完全に個人的なオナニーエントリーなんで興味ない方はすっ飛ばしてください。
これは完全に個人的なオナニーエントリーなんで興味ない方はすっ飛ばしてください。
実は最近ずっと心が沈んでいました。それは将来どのルートに自分をのせるか、定めきれなかったから。とにかくまだ学びたいことがたくさんあるから院に進学しようという決意は、入学当初から持っていたものの、どの領域で(とりあえず)やっていくかを決められなかった。この3年間、毎日問い続けてきた。時々自暴自棄になったりもした。興味はただただ拡散していった。どのスタートラインにも立てなくて、もう駄目かと思った。昨日、ひとつの授業を受けて、ふと迷いが取れた。これ以外の選択肢なら、一回きりの人生を最大限冒険することにはならないだろうと思った。
出た答えは、文化人類学。近年その学問的手法が徹底的に批判され、枯れた学問だと言われ、将来はないと断言され、学問じゃない文学だと罵倒され、文部省も予算を削減しようと動いたその領域、文化人類学。どん詰まりであればあるほど、チャンスがある。あえてそこに乗らざるを得ない気がする。むしろ自分がやっていることの意義がわからなければわからないほど、死に物狂いになれると思った。醒めたカッコつけができなくなると思った。たとえ食いっぱぐれても、ホームレスになればいい。辛かったら死ねばいい、妻子がいなければ。
続きを読む...April 05, 2004
宇宙で文系が必要とされる日
 宇宙エレベータに関連してひとつ。かつてシンポジウムで宇宙飛行士・毛利衛さんの話を聞いていて印象的だったのが、これからは人文・社会系も宇宙でより必要とされてゆくだろうという話でした。現在は技術開発がとにかく必要だから、「宇宙」は理系やテクノロジーの牙城みたくなっている。だがある一定の技術ベースができあがると、もちろん技術の進展具合と呼応しながらだけれども、そこにどのような文化を築くかということが問題となってくる。宇宙での政治や法律、芸術や倫理。だから、そのようなスパンでもって自身を展開してゆくと面白いかも、と仰っていた。「宇宙エレベータ」の記事で述べた『自分の「豆の木」を伸ばしながら』というのは、そのような意味も込めてのことです。ふと、思い出してしまったので。
宇宙エレベータに関連してひとつ。かつてシンポジウムで宇宙飛行士・毛利衛さんの話を聞いていて印象的だったのが、これからは人文・社会系も宇宙でより必要とされてゆくだろうという話でした。現在は技術開発がとにかく必要だから、「宇宙」は理系やテクノロジーの牙城みたくなっている。だがある一定の技術ベースができあがると、もちろん技術の進展具合と呼応しながらだけれども、そこにどのような文化を築くかということが問題となってくる。宇宙での政治や法律、芸術や倫理。だから、そのようなスパンでもって自身を展開してゆくと面白いかも、と仰っていた。「宇宙エレベータ」の記事で述べた『自分の「豆の木」を伸ばしながら』というのは、そのような意味も込めてのことです。ふと、思い出してしまったので。
宇宙エレベータ
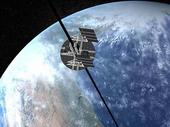 古くて新しいニュースだけれども最近知りときめいたので。「宇宙エレベータ」なるものが開発されているらしい。これは「エクアドルの西の赤道上に浮かぶ移動式の海上プラットフォームから、約10万キロ上方の宇宙空間まで伸びる幅1メートルの「リボン」を建設する」計画だ(Hotwired)。つまり海上の基地と宇宙ステーションをつなぐエレベータを作ろうという、にわかには信じがたいアイデアだ。この構想は、1895年ロシア(ソ連)物理学者のコンスタンチン・エドゥアルドビッチ・ツィオルコフスキーが著し、1959年に刊行されたものが発端とされているが、世間に広まったのは、SF小説「楽園の泉」(1979年、アーサー・C・クラーク)と、「星々に掛ける橋」(チャールズ・シェフィールド)がはじまりとされている。この「ジャックと豆の木」みたいな夢話は、なんと現在技術的にはそれほど実現不可能なものではないと考えられている。軽量で強いカーボン・ナノチューブという素材の開発により、開発は劇的に進歩したのだ。想像は現実を創造する。明るいものも、暗いものも。
古くて新しいニュースだけれども最近知りときめいたので。「宇宙エレベータ」なるものが開発されているらしい。これは「エクアドルの西の赤道上に浮かぶ移動式の海上プラットフォームから、約10万キロ上方の宇宙空間まで伸びる幅1メートルの「リボン」を建設する」計画だ(Hotwired)。つまり海上の基地と宇宙ステーションをつなぐエレベータを作ろうという、にわかには信じがたいアイデアだ。この構想は、1895年ロシア(ソ連)物理学者のコンスタンチン・エドゥアルドビッチ・ツィオルコフスキーが著し、1959年に刊行されたものが発端とされているが、世間に広まったのは、SF小説「楽園の泉」(1979年、アーサー・C・クラーク)と、「星々に掛ける橋」(チャールズ・シェフィールド)がはじまりとされている。この「ジャックと豆の木」みたいな夢話は、なんと現在技術的にはそれほど実現不可能なものではないと考えられている。軽量で強いカーボン・ナノチューブという素材の開発により、開発は劇的に進歩したのだ。想像は現実を創造する。明るいものも、暗いものも。
March 23, 2004
思考の恣意性?
テロについて書いた文章に対するEP end-pointさんの応答への、再応答。感謝です。先程長々と書いてしまったので簡潔に。
人間は平和主義な生き物ではない。闘い好きな生物でもない。皮相な性善説性悪説二元論は卒業すべし。「本来」という語を使いたいのであれば、本来そこに意味はない。善悪しかり。勝ち負けしかり。続きを読む...
大きく語るときに必ずや混入するナルシシズム
 「テロ」論への補足、「環境保護」の欺瞞に対するEP end-pointさんの応答への、再応答。わざわざありがとうございます。まず返信が遅れてしまったことをお詫びします。
「テロ」論への補足、「環境保護」の欺瞞に対するEP end-pointさんの応答への、再応答。わざわざありがとうございます。まず返信が遅れてしまったことをお詫びします。
理由はどうあれ、実際のリスク解析も何も考慮しないで「地球のため」「自然のため」というキャッチフレーズを掲げる人間はみな欺瞞屋だと受け取られうる見方を出してしまうのは浅慮な気がする。続きを読む...
March 16, 2004
「テロ」論への補足、「環境保護」の欺瞞
EP end-pointのAmasakiさんに、一昨日の「テロ絶滅はエイリアンに頼るしかない?」の中で用いた「弱肉強食」という俗説は科学的に妥当性が無いと指摘されました(EP end-pointとnew sphere!は進化と文化を考える上で極めて有意義なサイトで、かなりオススメ)。おそらく俺が血液型性格判断によって何かを論じられたら感じるの同じような意味で、違和感を覚えられたんだと思います。私日記に少々学問的フレーバーを加えたこのBlogの在り方も色々と考え直してしまいます。モラルとして。
続きを読む...March 13, 2004
テロ根絶はエイリアンに頼るしかない?
 昨日はスペインで生じたテロ事件を日本の危機という観点からのみ扱いましたが、今日は思い切って、自分の「テロ」というものに対する価値観のスケッチを描いてみます。自分の「テロ」観はこれまであえて伏せてきました。それは、ひとえに自分の言葉がリアリティを持ち得ないと考えてきたから。つまり、すぐそこにある身近なものとしてテロを感じることの無い日本人である自分は、どうしても「対岸の火事」的に「テロ」を考えるしかない。発する言葉に、肉体的リアリティが、圧倒的に無い。だから、沈黙してきた。この後ろめたさの中であえて語ります。
昨日はスペインで生じたテロ事件を日本の危機という観点からのみ扱いましたが、今日は思い切って、自分の「テロ」というものに対する価値観のスケッチを描いてみます。自分の「テロ」観はこれまであえて伏せてきました。それは、ひとえに自分の言葉がリアリティを持ち得ないと考えてきたから。つまり、すぐそこにある身近なものとしてテロを感じることの無い日本人である自分は、どうしても「対岸の火事」的に「テロ」を考えるしかない。発する言葉に、肉体的リアリティが、圧倒的に無い。だから、沈黙してきた。この後ろめたさの中であえて語ります。
人間ないし生物は基本的に争うものです。おのれの生存をかけて、戦う存在である。なぜなら、自然界は決して「平等」ではなく、弱肉強食の世界であるから。食われる恐怖に対抗するには、戦うしかない。抵抗しなければ、殺される。「万人の万人に対する闘争」が世界の真実の姿だとホッブスは語りましたが、この考え方に同意します。しかし、一人(一個体)で戦うよりは、集団を形成したほうが有利です。強くなる。だから、集団をどんどん拡大させてきた。人類が誕生した頃、ヒトという種は結束し、外的環境と戦ってきた。ヒトが増えてくると、今度はヒト同士が小集団を形成し、他の小集団と抗争した。同じような構造がその規模を増し、国家が誕生し、主権をめぐり争うようになった。
続きを読む...March 10, 2004
「浮気は悪か」と問えるか?
 殺人は悪か?浮気は悪か?正直は善か?さまざまな問いが設定されて、人々はあれこれ考え議論する。でもこれらの問いに対する答えは、実は「ケースバイケース」でしかあり得ないと考えられる。頭の中には、もしヒトラーが暗殺されていたらユダヤ人虐殺はどうなっていただろう、映画タイタニックにおける「浮気」、人の精神状態を気にしない暴力的な言葉が浮かんでくる。つまり、一般的な命題を問うことなどそもそも不可能なのではないか。ある問いは、「〜に対してどうであるか、〜という状況においてはどうであるか」というように、状況限定的にしか発することができないのではないか。
殺人は悪か?浮気は悪か?正直は善か?さまざまな問いが設定されて、人々はあれこれ考え議論する。でもこれらの問いに対する答えは、実は「ケースバイケース」でしかあり得ないと考えられる。頭の中には、もしヒトラーが暗殺されていたらユダヤ人虐殺はどうなっていただろう、映画タイタニックにおける「浮気」、人の精神状態を気にしない暴力的な言葉が浮かんでくる。つまり、一般的な命題を問うことなどそもそも不可能なのではないか。ある問いは、「〜に対してどうであるか、〜という状況においてはどうであるか」というように、状況限定的にしか発することができないのではないか。
こんな当たり前のことが、見過ごされやすい。問いを立ててあれこれ考えてみる。けれども、もし問い自体が間違っていたなら、そもそも答えは導きようがない。すべての思索は無意味となってしまう。問いを引き受けて考える以前に、その問い自体にこだわってそれが適切かどうか吟味すること。ここに多くの労力を割くことを、ないがしろにしてはいませんか?
March 08, 2004
対称性が嘘だとしたら世界はどうなる?
 某知り合い筋によると、ベイスターズ山下監督の御子息は今年電通にコネ入社らしいです。ベイスターズ共々なんだかな。さて、本題。世界には自明のものがたくさんある。たとえば対称性もそのひとつです。中心線をまたいで、右と、左。同じ座標に同じものが位置しているならば、基本的に左右に違いはないと考えられている。
某知り合い筋によると、ベイスターズ山下監督の御子息は今年電通にコネ入社らしいです。ベイスターズ共々なんだかな。さて、本題。世界には自明のものがたくさんある。たとえば対称性もそのひとつです。中心線をまたいで、右と、左。同じ座標に同じものが位置しているならば、基本的に左右に違いはないと考えられている。
ところで面白い話を聞きました。広告業界に精通しているわけじゃないので真偽は不明だけれど、聞いたところによれば、どうやら車のCMを作る場合、たとえばスポーツカーなら画面(フレーム)の右側から進入させる、セダンなら左側から侵入させる、みたいなセオリーが存在するらしい。同じ角度で進入させても、左右で印象が違うという。
もしこれが事実ならば、安定している世界の自明性がとたんに揺らぐことになる。右と左の違いは、実は気づいていないだけで、多くのものを規定しているのかもしれない。そんな世界を考えてみたら?――対称性に関する哲学的・物理学的・美学的・業界的etc...な文献は読んだことがないけれども、論文テーマをこれに設定しようかと考えてしまう。つまり、「見え」がいかに実質的な思考や印象に影響を与えるか。昨日の罫線ノートの話とも共通するけれど、そんなことにも最近関心があります。
罫線つきノートやBlogは思考の仕方を強制する
 ここ最近ポータル構築ツールのXoopsや情報集積ツールのPukiwikiなんかをサーバーに入れて試して遊んでました。色々なネットツールを弄んで感じるのはやっぱ、技術が人の思考や表現の仕方を大きく規定しているということ。
ここ最近ポータル構築ツールのXoopsや情報集積ツールのPukiwikiなんかをサーバーに入れて試して遊んでました。色々なネットツールを弄んで感じるのはやっぱ、技術が人の思考や表現の仕方を大きく規定しているということ。
このBlogだって、昔からサイトに訪れて下さった方はわかると思うけれども、Genの思考様式を大きく規定している。どこかからソースや商品や写真をひっぱってきて、それにコメントを付け加える。あるいは自分がBlog村の一員であることを自覚して、メタブログ的(ブログについて)話を書いてみたり。様式に染まった思考に行き詰って、更新が滞っています。初心に帰ろう。
面白い友達がいます。彼は講義を受けるとき、絶対に罫線つきの普通のノートを使わない。あくまで落書き帳みたいな、全くの白紙のメモを用いる。そこに書き殴る。「何でそんなもの使うんだ?」と聞いてみた、彼曰く、「罫線つきのノートは、罫線によって自分の考えが区切られ強制されるだろ?どの大きさで文字を書くか、どこに書くか、どんな順序で配置するか、それによってぜんぜん変わってくるんだよ?」。
続きを読む...February 25, 2004
東大生ストーカーとの奮闘記
ストーキングは暴力だ。圧倒的にしみったれた、腐った陰湿な暴力だ。では、そんな腐ったストーカーに狙われ、心中に影を抱えながら日々を過ごさねばならない人は、どうすれば良いのか?
前にも書いたけれども、友達がストーカー被害にあっているんですよ。で、電話越しにその男が名乗るところは「東大法学部○年のxxx」ってことらしく。繰り返される郵便受けへの手紙の投函、執拗な電話攻撃、その友達の女の子が一日に取った行動を細かく記録し報告する――
で、その子の近所に住んでいる俺は、もちろん然るべき役を買って出たわけですが、彼女は二つの行動を取った。第一に警察に相談、第二に東大のハラスメント相談所に相談。警察は「近辺のパトロールを強化する」という紋切り型の対応。そして相談所がまた腹立たしい所なんですね。電話越しにストーカーの男は「法学部の○○」と名前を名乗った。当然、実在の人物かどうかを確認することは、物理的にも彼女の精神的にも、事態の解決の上で不可欠なわけです。ところが、「最近個人情報は大事だという流れもあって、簡単に(その男の)身分照会に応じることはできない」なんて対応が返ってくる。挙句の果てに、「その個人を特定して実際に指導を行うまでには、何枚も書類を作成する必要があり、時間がかかる。具体的被害の少ない現状では、おそらく不可能でしょう」ときた。
続きを読む...February 24, 2004
第一印象と血液型の心理学
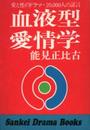 第一印象は大きい。これはどうしようもなく大きい。心理学的にも裏付けられて、大きい。
第一印象は大きい。これはどうしようもなく大きい。心理学的にも裏付けられて、大きい。
心理学的実験でその存在が実証されている、「確証バイアス」という心のある傾向。それは「自分がもっている仮説を確かめるときに、その仮説に合致する証拠を重視する傾向」を指す。わかりやすくいえば、自分が「こうだ!」と思ったら、その自分の考えと一致する証拠ばかりを探してしまい、それを否定するような証拠は見ないようにしてしまう思考の癖のこと。
初対面のとき、カッコイイ!と思う。するとその後、彼のカッコイイところばかり目につき、駄目なところは霞んでしまう。優秀だ!という印象にしろ、インチキ臭い!という印象にしろ、同じこと。だから初対面のときは、とにかく頑張る。もちろん後で印象は覆せるにしろ、それはコスト的に面倒なこと。
A型は几帳面。広く信じられている血液型性格判断。でもこれは、心理学的実験では、何度やっても、そんなことはないという結果になる(詳細はこちら)。とにかく、科学的にはまったく証明されない。おそらく先程の「確証バイアス」なるものが働いていて、「A型=几帳面」という面ばかり見てしまい、それを否定するような例は、見逃してしまう。
続きを読む...February 21, 2004
コンパ幹事論――心理学的に考えると
昨日はうちの心理学科全体のコンパを仕切ってきた。教授と院生に適度に気を配りながら、それでいてもガンガン飲み弾けて自分が一番楽しむのが、名幹事たるための条件かな。幹事のオーラは飲み全体の雰囲気に伝播してしまうから。幹事をやると、しんどいと同時に、どこか救われる。それにはおそらく、「状況が人を作る」ということが関係している。
一般に思われているよりも、どうやら人間は個人の性格を過大評価してしまい、状況の力の影響は過小評価してしまう、ということが心理学ではいわれています。たとえば、ネクラだと思われていた人がいざリーダーシップを発揮せねばならないポストにつくと、それなりにリーダーシップを発揮したりするということ。あるいは、しばしば、第二次世界大戦中の日本の軍国主義(全体主義)は日本人が持つ集団主義的傾向が原因だなどといわれたりするけれども、それよりも「経済的・軍事的に追い詰められた国家は全体主義的傾向に向かう」という状況的な力の方が大きかったのではないか、ということ。
続きを読む...February 18, 2004
飛行機墜落事故と、素敵な哲学者(後編)
二つの別々のものが思わぬとこでひとつに結びつくと、素敵を感じてしまう。恋愛だけじゃない。誕生日の偶然の一致や、出身が同じだったりすることも。とにかく、前編で書いた1985年のジャンボ機墜落事故が、ひとりの哲学者に偶然結びついた。彼の名は、内山節(たかし)。
February 16, 2004
飛行機墜落事故と、素敵な哲学者(前編)
この記事はできれば読んで欲しいです。純粋に皆さんの意見を聞いてみたい。昨日の記事で書いた520名が亡くなった飛行機(日航機)墜落事故についてちょっと調べていたら、いくつかの印象的なサイトにぶち当たりました。まず、わずか4名しかいなかった生存者のひとり落合由美さんの証言(サイトはこちら)について。ジャンボ機が落ちてゆき墜落するまでを淡々と語っているさまには、本当になにか突き抜けた印象を受ける。凄すぎると、逆に、淡々とせざるをえないというか。以下、印象的な部分を少々引用。
救命胴衣は飛行機が着水して、外に脱出してからふくらませることになっています。機内でふくらませてしまうと、体を前に曲げて、膝のあいだに頭を入れる安全姿勢がとれないからです。しかし、私の席の周囲では、ふくらませてしまったお客様が、四、五人いました。男の人ばかりです。 こういう場面になると、女の人のほうが冷静なようです。泣きそうになっているのは男性でした。これはとても印象深かったことです。(中略) 私は何も聞かれませんでしたが、制服を着ていたスチュワーデスはお客様からいろいろ質問されていました。「どうなるんだ」「大丈夫か」「助かるのか」。聞いていたのは男の方ばかりでした。続きを読む...
February 11, 2004
「言葉が生まれるべき場所」を探して――其の2
Blogを書いたり人と語ったりものを書いて生活するときに、自分の言葉を生み出す根拠となる場所が欲しいなぁ、どこにそれを求めりゃいいんだよ?という其の1の話に続く第2弾。先に其の1を読むか、興味のない方は読み飛ばしてくださいまし。まあまあ長いです、覚悟してください。ハチマキ締めてください。でもGenは好きな文章です。ちなみにタイトルをクリックすると、文章が多少読みやすくなります。
続きを読む...「言葉が生まれるべき場所」を探して―――其の1
自分の言葉の根拠はなにか?たとえばこうしてBlogを書くけれども、その言葉はどこから生まれてきたのか?ざっと考えつく限りでは
1.本や他のHPなど以前に読んだテクスト
2.生きる上での純粋な自分の人生経験
3.芸術などの感性を豊かにし言葉を触発するもの
「情報理論」なるものでは、ある情報の価値は、a.確実性、b.意外性が規定しているらしい。a.確実性とは、情報の確かさ。噂話よりは、論文に書かれていることのほうが信憑性が高く、情報価値が高い。b.意外性とは、情報の目新しさ・独創性。どこかで聞いた話は2度も聞きたくないわけです。
たとえば俺がAV女優だったら、おそらく仕事の話をするだけで読者はついてくる。2.の人生経験の情報価値が高いためです。でもしがない大学生としては、自分自身で、なにか言葉が生まれてくる場所を創り出すしかない。しかもGenは人文系の学者=言葉で飯を食ってこうとしている。どこから言葉を産み出そうか、と常々悩んでしまう。では、言葉はどこから生まれてくるのか?
続きを読む...January 28, 2004
期限から逆算せず、今を生きる人生。さよなら青い鳥?
寒さに手を抜かれると、腹が立つ。たくさん着込んで外に出て、なんか生暖かい感じがして、うっすら汗ばんだ時なんか、精神的に最悪。冬はとことん寒いほうがいい。貫かれて身がしまる感じが、快感。北海道とか行くと、ニヤけてしまう。
それと似てるかどうかは謎だけど、自分がだらしない時も、とことんだらしなくなるまでだらけてていいやー、とか思ってしまうことがよくある。中途半端より、徹底しろ、みたいな。外にも出ない、本も読まない、メールも返さない、ただぐたぐたのひととき。テレビならすぐ飽きるけど、ネットがある今は怖い。2chなんかみてると軽く一日がつぶれてしまう。この太宰治の『堕落論』の安いパロディみたいな考えは、でも、結局は自分への甘え。あれこれ理由をつけて、けじめのない自分を正当化するための、言葉たち。