Lovely now*
Menu
Categories
・
BLOG/ネット(7)
・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
Profile
Recent Entries
* 移転しました。
* お知らせ
* 株をめぐる言説の整理
* 「グローバリゼーション」の輪郭線part.1
* 信頼についてpart.1
* 柴田元幸が日本の現代小説を見立てると
* 自然保護運動への嫌悪感、を越えて
* パリの建築と景観、そして移民
* 夏の、音
* 恋愛とは美しき誤解
Syndicate
Notes
人間と動物の「乱交文化」
[ 大学生活と学問と語り]
『心の進化―人間性の起源をもとめて』冒頭の座談会より興味深かったものをいくつかメモ。
松沢(霊長類研究者):例えば、チンパンジーやゴリラには、アドレッセンス・ステライル(思春期不妊)という現象があるんです。思春期に交尾はするけれども避妊はしない時期がチンパンジーでもゴリラのメスでも2年くらいあります。この時期のゴリラは非常に乱交的になり、いろんな集団を渡り歩いて、いろんなオスと交尾するということがおこる。
船曳(文化人類学者):マリノフスキーの『トロブリアンド諸島』の研究にあるのですが、初潮以降に女の子と男の子たちが一種の乱交状態に入るんです。それが数年続く。子供が生まれないんですよ。やっぱりそのある時期を通り越して、そして今度は本当の大人になるという。だから僕は、人間が作り上げたいろいろな機能、細かなルールなどのために簡単には出てこないのだけれども、ときどきプツップツッと自然が噴き出すときがあると思っていて、それが例えば今の高校生の性に対するある感じや、日本人の避妊に対する態度とか、いろんなことに顕れていると思うんですね。
何事も「他のものと比較する」という行為を抜きにしては、探求したいものの特質を同定することはできない。過去との対比が「歴史」と「現代」を作った。異なる地域の人間との比較が、「文化」を創造した。あるいは、他人の考えを知ることによって、はじめて「自分」とはなんたるかをおぼろげながらに知ることができる。そして、「人間と、人間でないものを比較する」という営みは、さらなる次元を切り開き続けるように思われる。その意味で、進化論的な話はあまりに魅力的過ぎる。人文系の思想的・理論的な流れと、進化的知見の融合/反発は、絶対に探求し続けねばならないテーマなのだろう。両方への目配りを。船曳さんのいう「プツップツッ」を何とか構造化して説明できないものだろうか。

船曳:イギリス人の男に「子供と奥さんどちらかを助けなければいけない、という状況に陥ったとしたらどちらを助けるか」という質問をすれば「妻」と答え、女の人に聞けば「夫」と答えざるを得ないのだが、日本ではほとんど「子供」という。つまり、愛という形が日本とイギリスではぜんぜん違うといのです。(中略)
松沢:でも90年代、われわれ霊長類学者はチンパンジーがシロアリ釣りをするなんて乱暴なことはいわない。チンパンジーは確かにシロアリ釣りをするけど、それはゴンベ(地名)のチンパンジーがシロアリ釣りをするんであって、私が見ているギニアのチンパンジーは、シロアリをつまんで食べるけどシロアリ釣りはしないと。
船曳:文化人類学と一緒ですね。(種の内部の)文化の違いをいうわけだ。
松沢:文化と張りついた自然性という、種のレベルで決まっているわけではなくて、その種がいろいろな環境に適応していく中であらわれてくるもの。(中略)土地、風土、森、そこの食物生産量、そういったものがいかに社会を規定しているのか、これを読み解きたい。
動物にすら、同種でもそれぞれの生態的環境に応じた異なる「文化」が存在するという、明白な証拠の数々。人間が便利だから曖昧なまま用いてきた「文化」という概念は、人間以外の種が持つ「文化」というものと比較されることによって、より解体されていくのだろう。それは生態系へどんどん拡散していくようにも思われる(ex.マーヴィン・ハリス)。その上で、人間をとりまく「意味の世界」を考えたとき、いったい何が見えてくるのだろうか。
Post a comment
Trackback


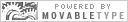
***→