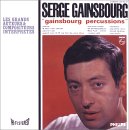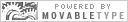・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
July 04, 2005
恋愛とは美しき誤解
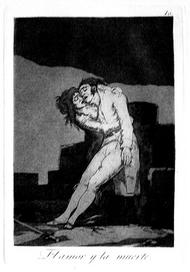 ときどき立ち返ると、やはり亀井勝一郎は腑に落ちるな。彼の言葉に触れると、亡くなった祖父を想い出す。小学校すら廃校になるような田舎の漁村で、商店を営みながら、商売気もそぞろに、言葉の魔力に取り憑かれていた、その姿を。そういえばこれも祖父がくれた本だった。以下はすべて、『愛の無常について』より引用。
ときどき立ち返ると、やはり亀井勝一郎は腑に落ちるな。彼の言葉に触れると、亡くなった祖父を想い出す。小学校すら廃校になるような田舎の漁村で、商店を営みながら、商売気もそぞろに、言葉の魔力に取り憑かれていた、その姿を。そういえばこれも祖父がくれた本だった。以下はすべて、『愛の無常について』より引用。
恋愛とは美しき誤解であり、誤解であって差支へありませぬ。そして結婚生活とは恋愛が美しき誤解であったことへの惨憺たる理解であります。理解は犠牲を要求します。絶えず理解を疑うことが、理解に近似する唯一の道です。人間はいったい、何を知りうるのでしょうか。
恋する人間をごらんなさい。彼らはみな天才的に振舞っているではないか。恋愛は、芸術と同じように、破滅と復讐の上に成立する快楽なのです。だから美しい。愛し合う二人の恋は、ほとんど決して同じではない。恋愛とは、本質的には片想いなのです。「想像されたものはすべて実在する」という恋の狂気なのです。続きを読む...
July 02, 2005
相手の気持ちを考えつつ感情のままに生きること
 垂れ流しから移植。今回の恋愛で得たもの失ったもののまとめ。
垂れ流しから移植。今回の恋愛で得たもの失ったもののまとめ。
別れ際に、「もう少し感情のままに生きてもいいんじゃないのかなぁ‥」と言われた。感情のままに生きること。それは、歳を重ねるごとに、色々なことを知り考えるたびに、一番失ってきた、でも実は一番大切なこと。
続きを読む...April 14, 2005
ピルのはなしに続いて。避妊/男/女
 前回のエントリーは繊細なテーマであるにも関わらず書き出しからして軽薄だったし、確実にある読み方をされるだろうなと思っていたら、やはりそのような読み方をされたみたいなので(それを「誤解」として自分を弁護するつもりは全くないですが)、もうひとつだけ書かせてください。まず、葵さんのコメントを全文引用しておきます。
前回のエントリーは繊細なテーマであるにも関わらず書き出しからして軽薄だったし、確実にある読み方をされるだろうなと思っていたら、やはりそのような読み方をされたみたいなので(それを「誤解」として自分を弁護するつもりは全くないですが)、もうひとつだけ書かせてください。まず、葵さんのコメントを全文引用しておきます。
ホント、これで万全だと思ってしまう男だからこそ男なのか?判れといっても想像つかないでしょうね。こんなことで産婦人科の門をくぐらなけりゃならない情けなさを。何かあっておたおたしてくれた方がどれだけ人間的か、結果さえ押さえればいいととりすましている男に付き合わされる女性は気づかないうちに壊れてきそうです。良心の呵責を負いたくないための姑息な手段としか思えません。それにしても妊娠も病気も、この人のなら後悔しない、と思える相手とsexしていないのが不思議。それぞれ価値観は違うと思いますが、恋愛観こねくりまわすまえに心震える恋愛をこそじっくり味わってほしいと思います。続きを読む...
April 07, 2005
心の片隅にモーニングアフターピルを
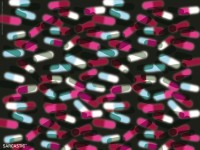 そういえばこの前、かなり久々に合コンをした。相手は看護婦だったのだが、その場でもリサーチを怠らなかった友人に思わず頬が緩んでしまう。その中で少し気になったのが、以下の箇所。
そういえばこの前、かなり久々に合コンをした。相手は看護婦だったのだが、その場でもリサーチを怠らなかった友人に思わず頬が緩んでしまう。その中で少し気になったのが、以下の箇所。
Q、(産婦人科の方へ)中絶とかどのくらいの頻度で行われているんですか?続きを読む...
A、うちの病院では、ほぼ毎日来ますね(yasuchan驚く)。
January 09, 2005
最高の相手を嗅ぎ分ける数学的戦略
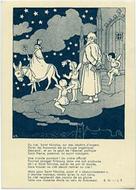 今日はタール1mgで軽めに。「37%ルール」を御存知だろうか。有名なのでもしデジャビュならスルーしてください。バイトで面接する店長、あるいは結婚紹介o-netの会場で真剣なまなざしが会場を舐め回して定まらないあなたは必見。懐かしの「ねるとん」とか。マジ懐かしー。佐竹とワンダフルの司会の女がカップルになったりしてましたよね。
今日はタール1mgで軽めに。「37%ルール」を御存知だろうか。有名なのでもしデジャビュならスルーしてください。バイトで面接する店長、あるいは結婚紹介o-netの会場で真剣なまなざしが会場を舐め回して定まらないあなたは必見。懐かしの「ねるとん」とか。マジ懐かしー。佐竹とワンダフルの司会の女がカップルになったりしてましたよね。
January 07, 2005
闘争せよ!お金で「換えない」価値がある
 明けましておめでとうございます。15万もの人々が地球と歴史に呑み込まれて幕を開けた2005年。言葉がないですね。とにかく今年も何卒宜しくお願い申し上げます。まぁ新年の抱負なんて小泉の答弁並みにロクなもんじゃないんですが、個人的には物腰の柔らかさを身につけたいと考えた元旦でした。
明けましておめでとうございます。15万もの人々が地球と歴史に呑み込まれて幕を開けた2005年。言葉がないですね。とにかく今年も何卒宜しくお願い申し上げます。まぁ新年の抱負なんて小泉の答弁並みにロクなもんじゃないんですが、個人的には物腰の柔らかさを身につけたいと考えた元旦でした。
さて。クリスマス前に書いた「一番無駄なものが、一番ロマンティックである」にコメントを寄せてくださった方がいました。彼女の指摘が論点を炙り絵のように見せてくれます。どうもありがとうございました。伝えたかった点をあらためて強調しておきます。
驚嘆すべきなのは、「恋愛」こそ、合理的・科学的な意味でも遊びが残されている領域だということです。ふつう科学や(経済的)合理性の世界に芸術やジョークやウィットが入り込む余地はありません。
続きを読む...December 23, 2004
一番無駄なものが、一番ロマンティックである。
 さーいよいよクリスマスですよ。そこで。反響を頂いた「とりあえず究極の恋愛論」シリーズ(part.1〜part.5)の、クリスマス直前講習。ロマンティックさの本質は、「無駄さ」である。進化論の初級レベルの理論を援用&紹介しつつ。
さーいよいよクリスマスですよ。そこで。反響を頂いた「とりあえず究極の恋愛論」シリーズ(part.1〜part.5)の、クリスマス直前講習。ロマンティックさの本質は、「無駄さ」である。進化論の初級レベルの理論を援用&紹介しつつ。
クジャクの羽の話を知っているだろうか?クジャクのオスの羽は美しい、見入る者を魅せる。メスは美しい羽を持っていない。オスはなぜこんな羽を持っているのか。生存上は、明らかに不利だ。目立つということは、敵(捕食者)に見つかりやすいということ。さながらカメレオンのように、背景に同化できる方が有利なはずなのに。
続きを読む...June 14, 2004
とりあえず究極の恋愛論 - 補講
とりあえず究極の恋愛論Finalでは、抽象的に抉り出された恋愛の構造(恋愛論)ではなく、恋愛の経験その一瞬一瞬のうち、たったひとつの物語にこそ恋愛の本質があることを述べました。それでも懲りないあなたにおくる、とりあえず究極の恋愛論ブックガイド。
続きを読む...June 13, 2004
とりあえず究極の恋愛論Final
 大雑把にいえばとりあえず究極の恋愛論part.1では恋愛に関する個人の心理的側面を、part.2では社会的側面を、part.3では実践的側面を、part.4では哲学的側面を語ってきました。さていよいよ最終章。恋愛論のまとめと、実際の恋愛そのものについて。おそらくこれが恋愛の本質。
大雑把にいえばとりあえず究極の恋愛論part.1では恋愛に関する個人の心理的側面を、part.2では社会的側面を、part.3では実践的側面を、part.4では哲学的側面を語ってきました。さていよいよ最終章。恋愛論のまとめと、実際の恋愛そのものについて。おそらくこれが恋愛の本質。
June 12, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.4
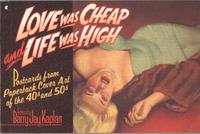 とりあえず究極の恋愛論part.1で「相手を好きになるとはどういうことか」、part.2で「社会制度として恋愛」、part.3で「相手を惚れさせるには?」とあれこれ書いてきました。今回は「愛」のいささか深い次元についてのおはなし。哲学的議論嫌いな方にはキツい記事かもしれません。無理ならパスしてください。ただ、恋愛と芸術をつなげる場合や、愛を深く論じる際には必要な話かなという気もします。次回フィナーレの予定。――「神様が僕を見るように、僕が彼女を見てあげることができるとき、僕は彼女を愛しているんだ」
とりあえず究極の恋愛論part.1で「相手を好きになるとはどういうことか」、part.2で「社会制度として恋愛」、part.3で「相手を惚れさせるには?」とあれこれ書いてきました。今回は「愛」のいささか深い次元についてのおはなし。哲学的議論嫌いな方にはキツい記事かもしれません。無理ならパスしてください。ただ、恋愛と芸術をつなげる場合や、愛を深く論じる際には必要な話かなという気もします。次回フィナーレの予定。――「神様が僕を見るように、僕が彼女を見てあげることができるとき、僕は彼女を愛しているんだ」
June 08, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.3
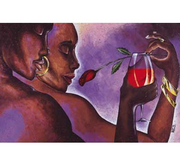 とりあえず究極の恋愛論part.1とpart.2の続編エントリー。もしこれを読むならば先にそれらを読んでくださいませ。本当に書きたいことはまだまだ書けずじまい。ここで、これまで書いたことを少々実践的なことにつなげてみたい。つまり、「相手を惚れさせる」「恋愛を長続きさせる」にはどうすればいいのか?
とりあえず究極の恋愛論part.1とpart.2の続編エントリー。もしこれを読むならば先にそれらを読んでくださいませ。本当に書きたいことはまだまだ書けずじまい。ここで、これまで書いたことを少々実践的なことにつなげてみたい。つまり、「相手を惚れさせる」「恋愛を長続きさせる」にはどうすればいいのか?
June 07, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.2
 とりあえず究極の恋愛論part.1を先に読んでくださいませ。ヨゴレに徹して恋愛論を書いてます。
とりあえず究極の恋愛論part.1を先に読んでくださいませ。ヨゴレに徹して恋愛論を書いてます。
さて、今回は彼氏/彼女という「制度」について考えてみたい。いわば恋愛の制度論だ。言い換えれば、相手を好きということと、相手と付き合うということに違いはあるのか?セフレと恋人の違いは?
続きを読む...June 06, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.1
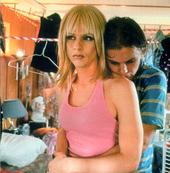 今日また不思議なセリフを聴いてしまった、「あの人は私のこと好きなんじゃなくて、恋してる自分に酔ってただけなんだよ、結局は」。強烈な違和感を感じた。何だ、それは。相手を好きだということと、相手を好きな自分が好きということは、全く同じ。ではそもそも好きってなんだ?恋って何だ?愛ってなんなんだ?「とりあえず」究極の恋愛論。1.なぜわたしは誰かを好きになる?2.制度としての恋愛論 3.惚れさせるには?4.恋愛と永遠――哲学・芸術・宗教と「愛」5.「好き」と「愛」の違い・恋愛の本質とは何か、という流れで。今日は1.について。
今日また不思議なセリフを聴いてしまった、「あの人は私のこと好きなんじゃなくて、恋してる自分に酔ってただけなんだよ、結局は」。強烈な違和感を感じた。何だ、それは。相手を好きだということと、相手を好きな自分が好きということは、全く同じ。ではそもそも好きってなんだ?恋って何だ?愛ってなんなんだ?「とりあえず」究極の恋愛論。1.なぜわたしは誰かを好きになる?2.制度としての恋愛論 3.惚れさせるには?4.恋愛と永遠――哲学・芸術・宗教と「愛」5.「好き」と「愛」の違い・恋愛の本質とは何か、という流れで。今日は1.について。
1.なぜわたしは誰かを好きになる?
便宜的に愛/恋の区別はひとまず保留。人に恋心を抱くとき、あえて分けるならば、その理由はおおまかに二つあるといえよう。一つはa. 性的魅力にまつわるもの、もう一つはb. (相手が)自分のアイデンティティを与えてくれることに関するもの。
a. 性的魅力は、人間のいわば「本能」と呼ばれるものに関連している。 人間も進化を経て誕生したひとつの「種」/ヒトという動物であるならば、恋愛感情も進化的に形づくられてきたはず。女性ホルモン、エストロゲンが多いと胸が大きくなる。だから胸が大きい女性は人気が出やすい(「出やすい」ということは、それがすべてではないということ。これは人間の救いかも)。セックスしたいという感情。相手の体臭にドキドキすること。男らしい筋肉に感じるドキドキ。セックスすると好きになる。酔った勢いでしたキスの記憶が頭から離れなくて、その人のことを好きになる。
b. (相手が)自分のアイデンティティを与えてくれることに関するもの。これはつまり「優しいからあの人が好き」だとか「一緒にいると素の自分でいられる」だとか「その人に会うために生きている」だとか「あの人は尊敬できる」だとか「あたしの帰る場所だからね」だとか「あいつのこと放っておけないんだよな」とか「だって超カッコイイし(可愛いし)」とか「趣味があうんだよね」、「オシャレだから」なんて話に関するもの。
続きを読む...June 02, 2004
あなたが触れて、はじめてわたしが存在する
 ラカンについて考えていてふと面白いことを知ったので。いわば実験心理学的な「赤ちゃん学」から精神分析家・ラカンの「鏡像段階論」を検討するとどうなるか―――ラカンの言うように、わたしは鏡を見ることによってはじめて「自分はひとつの統一された形を持った<私>である」ことを知るのか?それとも実験心理学的にはラカンの鏡像段階論は誤りであるのか?赤ん坊を持つ母親の方もこれは要注目ですよ。あるいは最後まで読めばセックスの凄さの理由が少しはわかるかも。
ラカンについて考えていてふと面白いことを知ったので。いわば実験心理学的な「赤ちゃん学」から精神分析家・ラカンの「鏡像段階論」を検討するとどうなるか―――ラカンの言うように、わたしは鏡を見ることによってはじめて「自分はひとつの統一された形を持った<私>である」ことを知るのか?それとも実験心理学的にはラカンの鏡像段階論は誤りであるのか?赤ん坊を持つ母親の方もこれは要注目ですよ。あるいは最後まで読めばセックスの凄さの理由が少しはわかるかも。
国際的に活躍する極めて優秀な心理学者、下條信輔による『まなざしの誕生――赤ちゃん学革命』という本がある。主に実験心理学的に「赤ちゃん」を考察した、実に面白い一冊だ。その一冊から「鏡と<鏡を見る私>」というテーマに関して興味深いところを抜き出しておく。
1)猫・犬・鳥類・猿・は鏡の中に映っているものが実は自分の分身であるということを認識できない。 2)チンパンジー・オラウータンは自己認識ができる。3,4日くらい鏡に慣れると、鏡の中の自分に対して「まるでほかの個体がそこにいるかのような<社会的反応>がなくなり、人間と同じような<自分に対する反応>を示すようになる」。 3)これが本当の意味での「自己認識」かどうか確認するため奇想天外な実験が行われた。「まず、鏡に十分慣れ親しませてから、麻酔でチンパンジーは眠らされる。次に、完全に無味無臭で、皮膚につけてもゴワゴワしたりしないような特別な染料を使い、チンパンジーの顔の一部を真っ赤に、けばけばしく化粧してしまう」。この哀れな<歌舞伎役者>は、目を覚まして鏡を見ると、「決して鏡の中の顔に手を伸ばしたりはせず、ほんものの(自分の)顔の赤い部分をこすったり、ひっかいたり、またそのあとでその指をじっとみつめる、鼻へ持っていく、などの行動がみられた」。 4)生まれたときから完全に隔離されて育てられたみなし子チンパンジーに同様の実験をしても、このような自分自身に対する探索の行動はみられなかった。 5)このことは自己認識の芽生えが、他人(他猿)の存在を前提としていることを示す」。
さらにここからが面白い。母親、必見。この論文に先立った実験で、研究者は、生後すぐに親から隔離されて育てられた、一歳半前後の幼いチンパンジー三匹を、ふたつのオリで育てた。三匹のうち二匹は同じオリの中で、自由にじゃれあったり、取っ組み合ったりして遊ぶことを許された。残りの一匹はもうひとつのオリに入れられ、ほかの二匹と一緒に遊ぶことはできなかったが、彼らの姿は見ることができた。つまり触れあいはないが視覚では他者を認識している状態だ。このようにして三匹を一ヶ月ほど育てた後、鏡に十分慣れ親しませた上で、例の<歌舞伎役者>のやりかたで実験を行った。その結果、一緒に育てられた二匹のチンパンジーは、ふつうの個体と同じような自己認識の反応(ex.自分の頬をひっかく)をみせたが、対照的に、ひとりぼっちのチンパンジーではそのような反応がまったく見られなかった。つまり、鏡の中に「自分」を見出すためには、視線による社会的交流だけでは不十分で、からだの直接的な接触がなくてはならないことがわかるのだ。
これはきわめて重要なことを示唆している。つまり、からだの接触なしで育てられた子供は、「自分」をはっきりと確立することはできない。そして他人と社会的に正常な交渉を持つことができなくなるだろう。いかにスキンシップが大切か。文字通りの、スキンシップ。
では、なぜこういう結果になるのか。「自分の腕をつまんでみたときと、他人の腕をつまんでみたときとでは――からだに起こる感覚はまったく違う。<さわり>同時に<さわられている>感覚があるのは、自分のからだだけである」。そして腕は鏡がなくとも自分で見ることができる。鏡がなくとも自己認識は成立しうるだろう。また「自分の頬や背中をつまんだときは、直接目には見えないけれども、からだに起こる感覚としてはやはり、自分の腕に似ているといえるだろう」(サルトルなどの「即自」と「対自」の概念?)。つまり、「子供にとって、一番教育的なものは、自分自身やほかの人たちのからだである」
文字通りの「身体感覚」が<わたし>の根底にあり、私を<わたし>たらしめている。見える腕と感じられる腕との関係。さあ、ラカンの鏡像段階論を考えてみよう。ラカンのいうように「鏡体験」のおかげで自己認識が成立するのではない。むしろ反対に、体感覚を通じた学習の結果、「鏡像認知」が可能になるのである。からだが先立つ。またラカンのいうように、ばらばらの身体興奮の集まりにすぎないいわば人間以前の存在が、鏡の中にまとまった像としての<わたし>を発見するのではない。すなわち「感覚同士が結びつく」のではなくて、「感覚同士ははじめから結びついている」。自分自身のからだと他人のからだをぶつけあって遊ぶことが、未分化の世界から分化した世界へと進む、決定的な足がかりとなる。身体感覚を通じて<わたし>を知ってはじめて、主体は鏡の中に<わたし>を発見することができるのだ。
さて、だからといって、ラカンの理論はまやかしだなどと言うつもりは毛頭ない。ラカンの理論はむしろ記号論的な意味で、すなわち<わたし>の内実は<他者>に私を重ね合わせることによってしか生まれてこないという意味で、また象徴が持つ役割を言説的に権威づける意味で、きわめて意義を持っているように思われる。<象徴界><対象a>は「使える」概念だ。だがしかし、発達論的な意味において、あるいはそもそもの人間の根源としてのカオスを考える上で、「鏡像段階論」に依拠しすぎることは少々危ういといわざるをえない。思想的に意味の地平を切り拓く上では有効であっても、それに基づいて実際に治療的介入を行うことには少々抵抗を感じてしまう。
セックスが根源的というのはこのような意味においてなのかもしれない。スキンシップこそが原初の私の感覚を与えてくれるものであるならば、肉体的な触れ合いにこそわたしは安らぎと戦慄を感じることができるだろう。ラカンの話にしろセックスの話にしろ、諸刃の剣をうまく振りかざしながら自分なりの意味体系を築いてゆきたいと強く感じた、6月1日。原宿駅にはもう紫陽花。
February 23, 2004
恋と芸術と永遠性と
亀井勝一郎 『愛の無常について』(講談社文庫、1971)を読んではっとしたことを少々。いや、たまたま本棚で見つけたら、これがえらく魅力的な言葉の海で。
「人間的愛にとって、最大の敵とは、時間そのものかもしれませぬ。」「愛するということは、全自己をあげて永遠に愛しようとすることでなけばならぬ。愛の可能性とは、愛の永遠性の可能性のことです。永遠に愛することを欲しない愛、いわば時間的に限定を設けた愛など存在するでしょうか。(中略)みな永遠です。愛とはその誓いなのですから。」「永遠性を今に完成させるためには、死を選ぶ以外にない。死は人間的時間の終焉です。死が愛の完成の証明となるのであります。(中略)失恋者の自殺は、恋を失った絶望によって、自己の恋の絶対性を確信したものの自己証明です。」
自分は、つきあってても「半年持つのかこれは」とか冷静に考えてしまう種の人間なんですが、それでもやっぱ「ずっと一緒にいたい」という気持ちがなければ、その恋は嘘なんじゃないかという気もする。恋心の真相とはきっと、「この恋が永遠である」ということは信じていなくても、今、この瞬間において「永遠でありたい」と思う気持ちなのだろう。そんなことをふと考えていたら、著者の亀井さんは見事にそのことを言い当てる。
続きを読む...February 21, 2004
Should it be last call ?
互いに大きな気持ちを残したまま別れるのって、不思議。気持ちが切れたっていうより、「別れなきゃいけない」という義務感に引っ張られて後戻りできないところまで来てしまった感じ。出会いがタイミングなら、おそらく別れも時には気持ちを超えたタイミングに支配される。両方が振られた気分?振り返ってどう感じるのかはわからないけれど、こんなに綺麗で甘い別れ際ははじめてだ。動揺。さてと、やるべきことに取り組むか。
February 18, 2004
戒め
相手のことを大切に想うって、相手を気遣い尊重することとはまた違うんだよな。わかってるつもりでわかってなかった。もちろん俺は根本的に不干渉放置プレイ主義で、誰かみたいにできないし生き方は変えられない。でも、今回は、うざいと思われることを引き受けて自分の信念貫いて強引に押し通すべきだった。そうしないってことは、結局根本的な部分で相手のことを考えてなかったのかもしれない。たとえあれだけ忙しくても。言い訳にすらならない。最後の最後で深いなにかを失わせてごめんな。ほんとに。でも無駄にはしない。以上、戒めのメモ。今までありがとう。
February 07, 2004
今の恋人にHIVを伝染される?
恋人に伝染された例を身近に一件知ってます。そこでちょくちょく正しい性知識シリーズ第1弾。生きてく上で自衛のため最低限必要なエイズ知識の再確認。すぐそこにあるHIV感染。
★まずセックスなどでHIVに感染。感染後、短くて6カ月位から長い場合は15年以上の潜伏期間を経た後、エイズを発症。発症すると、身体の抵抗力が弱まり様々な病気にかかり、非常に苦しい毎日。
★HIVは主として血液・精液・膣分泌液によって感染。だからフェラチオ・クンニでも感染する危険性あり(≠ゴムありセックスは安全)。
★感染の可能性があったときから3ヶ月たたないと、HIVに感染したかどうかの確実な判定ができない。だからすぐ検査してもダメ。この期間に輸血すると、HIV感染血液が検査で弾かれず通ってしまう。
★疑わしきときは迷わず簡単に検査。保健所なら、完全匿名・完全無料(保健所リスト)
★薬でエイズの発症はかなり抑えられるが、薬代がシャレにならない。
★「先進国」でのHIV感染伸び率は日本が一番高い。首都圏に感染者がダントツ多い。HIV感染の経路は、累計で異性間のセックス(計2369人)、同性間のセックス(計2118人)と、異性間セックスの方が多い!だから日常のセックスも結構怖い。世界の状況についてはこちら。南アではセサミストリートにも感染者役が登場。
★↓風俗はマジで怖い。
February 05, 2004
January 28, 2004
結婚について其の3。好きと重さとバランスと
結婚について其の1からはじまるSkywardさんのBlogとの結婚についての議論の延長。男は守りに入るのか?
男子よ!なぜこうも「(社会に)縛られ」て「抜け出せない」ことや「守りに入る」ことにこだわる!?
別に結婚したからって守りに入る必要ないし(女子が男子を守ってあげるし)、抜け出さなくちゃならないわけでもない(そもそもそんなに抜け出したいのか!?)と、一女子としては思ってしまうのだけども。
本気で相手のことを好きであればあるほど、不幸にはしたくない。これが一番大きい。結婚することは、自分が制限されるだけじゃなく、相手をも制限すること。というか、男は女の、女は男の将来を、ある程度預かる行為だと思う。そして何度も書いているけれども、子供ができると後に引き返すことはできない。
続きを読む...
結婚について其の2。自由vs制限?それとも‥
実はskywardさんのblogで、昨日書いた結婚について其の1が取り上げられて、コメントやトラックバック含めて色々な反応がありました。いろいろと誤解された面もあったようです。そこで、それへの返答の意味も込めて、結婚について其の2を予定より早く書きます。これもあくまで一大学生の意見です。ちなみに自分は結婚したいと凄く思う人間です。ただし、35歳くらいに。
まず3人の意見をそれぞれ要約すると、
続きを読む...結婚について、其の1。(恋愛への社会の混入?)
結婚とは何か?恋愛とはどう違うのか?あくまで一大学生から見た結婚について。結婚観のスケッチ。
結婚と、恋愛。それほど違わない、と個人的には思う。二人がともに、寄り添おうとする試み。けれど、結婚となるととたんに話がでかくなる気がする。ある種の重さを抱え込む。では、その「重さ」の正体とはいったい何か?それはおそらく、「社会」というもの。まず、国に届出をするということ(社会=国家の制度に巻き込まれる)。そして、自分の家族、相手の家族を激しく巻き込むということ。儀式としての、結婚式。金もかかる。
「社会」とはなにか?それはおそらく、自分がその中にいるけれど、自分じゃコントロールできないもの。国だってそう、家族だってそう。そして「バツイチ」という「社会」的評判が、いったい自分にどういう影響を及ぼすのか、想像もつかないしコントロールもできない。
恋愛ははじめ、あらゆる意味において自由だ。出会って、2回遊んで、「つきあおっか?」「うん」となったその時、二人はほんとに自由だ。そこには純粋なる関係がある。でも、徐々にいろんな「社会」が混入をはじめる。二人の純粋なる関係は、だんだん「社会」に縛られてゆく。
駆け引き無き恋は甘やかし。
駆け引きのない恋をしたい、なんて声をたまに聞くけど、恋愛は駆け引きだ。断言する。というか、駆け引きを否定するやつは、本気で恋をする気があるのかと問いたい。本気で人と関わろうとする気があるのかと問いたい。くっつきすぎたら腐る、離れすぎたら消えてしまう。その両極の間、中庸の部分に踏みとどまろうとするあがきこそが、駆け引きだ。
その関係を長続きさせたいなら、あれこれ考えて作為して優しくしたり冷たくしたり駆け引きした方がよっぽど正々堂々としている。近過ぎると見えなくなる、遠すぎるとわからなくなる。だから、相手と適切な距離を保とうとするその努力=駆け引き。一番相手に対してリスペクトを持った接し方じゃないだろうか。あれこれやって、その結果を、自分で被る。駆け引きに失敗して、恋が終わって、酒におぼれて、朦朧と考える。次は、もっとうまい駆け引きが、できることを祈りつつ。
それでも結局なるよーにしかならんという真実は肺の裏側にしまって。
#なんていま恋が消えたみたいな書き方。関係なく。最近レポートに行き詰るとやたらとページデザインを弄る癖が。でもCSSの知識の限界でイメージ通りにいかない。妥協。そう、結婚について書いてくれという某リクですが、も少し時間ください。なかなかまとまらない。そこで、こういう結婚の姿もあるよということで‥(半分ネタ)
旦那をメールでオーダーしよう!
俺、ヴァンパイアになるから、と夫がカルトに入信(写真にかなりわらた)