・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
あなたが触れて、はじめてわたしが存在する
 ラカンについて考えていてふと面白いことを知ったので。いわば実験心理学的な「赤ちゃん学」から精神分析家・ラカンの「鏡像段階論」を検討するとどうなるか―――ラカンの言うように、わたしは鏡を見ることによってはじめて「自分はひとつの統一された形を持った<私>である」ことを知るのか?それとも実験心理学的にはラカンの鏡像段階論は誤りであるのか?赤ん坊を持つ母親の方もこれは要注目ですよ。あるいは最後まで読めばセックスの凄さの理由が少しはわかるかも。
ラカンについて考えていてふと面白いことを知ったので。いわば実験心理学的な「赤ちゃん学」から精神分析家・ラカンの「鏡像段階論」を検討するとどうなるか―――ラカンの言うように、わたしは鏡を見ることによってはじめて「自分はひとつの統一された形を持った<私>である」ことを知るのか?それとも実験心理学的にはラカンの鏡像段階論は誤りであるのか?赤ん坊を持つ母親の方もこれは要注目ですよ。あるいは最後まで読めばセックスの凄さの理由が少しはわかるかも。
国際的に活躍する極めて優秀な心理学者、下條信輔による『まなざしの誕生――赤ちゃん学革命』という本がある。主に実験心理学的に「赤ちゃん」を考察した、実に面白い一冊だ。その一冊から「鏡と<鏡を見る私>」というテーマに関して興味深いところを抜き出しておく。
1)猫・犬・鳥類・猿・は鏡の中に映っているものが実は自分の分身であるということを認識できない。 2)チンパンジー・オラウータンは自己認識ができる。3,4日くらい鏡に慣れると、鏡の中の自分に対して「まるでほかの個体がそこにいるかのような<社会的反応>がなくなり、人間と同じような<自分に対する反応>を示すようになる」。 3)これが本当の意味での「自己認識」かどうか確認するため奇想天外な実験が行われた。「まず、鏡に十分慣れ親しませてから、麻酔でチンパンジーは眠らされる。次に、完全に無味無臭で、皮膚につけてもゴワゴワしたりしないような特別な染料を使い、チンパンジーの顔の一部を真っ赤に、けばけばしく化粧してしまう」。この哀れな<歌舞伎役者>は、目を覚まして鏡を見ると、「決して鏡の中の顔に手を伸ばしたりはせず、ほんものの(自分の)顔の赤い部分をこすったり、ひっかいたり、またそのあとでその指をじっとみつめる、鼻へ持っていく、などの行動がみられた」。 4)生まれたときから完全に隔離されて育てられたみなし子チンパンジーに同様の実験をしても、このような自分自身に対する探索の行動はみられなかった。 5)このことは自己認識の芽生えが、他人(他猿)の存在を前提としていることを示す」。
さらにここからが面白い。母親、必見。この論文に先立った実験で、研究者は、生後すぐに親から隔離されて育てられた、一歳半前後の幼いチンパンジー三匹を、ふたつのオリで育てた。三匹のうち二匹は同じオリの中で、自由にじゃれあったり、取っ組み合ったりして遊ぶことを許された。残りの一匹はもうひとつのオリに入れられ、ほかの二匹と一緒に遊ぶことはできなかったが、彼らの姿は見ることができた。つまり触れあいはないが視覚では他者を認識している状態だ。このようにして三匹を一ヶ月ほど育てた後、鏡に十分慣れ親しませた上で、例の<歌舞伎役者>のやりかたで実験を行った。その結果、一緒に育てられた二匹のチンパンジーは、ふつうの個体と同じような自己認識の反応(ex.自分の頬をひっかく)をみせたが、対照的に、ひとりぼっちのチンパンジーではそのような反応がまったく見られなかった。つまり、鏡の中に「自分」を見出すためには、視線による社会的交流だけでは不十分で、からだの直接的な接触がなくてはならないことがわかるのだ。
これはきわめて重要なことを示唆している。つまり、からだの接触なしで育てられた子供は、「自分」をはっきりと確立することはできない。そして他人と社会的に正常な交渉を持つことができなくなるだろう。いかにスキンシップが大切か。文字通りの、スキンシップ。
では、なぜこういう結果になるのか。「自分の腕をつまんでみたときと、他人の腕をつまんでみたときとでは――からだに起こる感覚はまったく違う。<さわり>同時に<さわられている>感覚があるのは、自分のからだだけである」。そして腕は鏡がなくとも自分で見ることができる。鏡がなくとも自己認識は成立しうるだろう。また「自分の頬や背中をつまんだときは、直接目には見えないけれども、からだに起こる感覚としてはやはり、自分の腕に似ているといえるだろう」(サルトルなどの「即自」と「対自」の概念?)。つまり、「子供にとって、一番教育的なものは、自分自身やほかの人たちのからだである」
文字通りの「身体感覚」が<わたし>の根底にあり、私を<わたし>たらしめている。見える腕と感じられる腕との関係。さあ、ラカンの鏡像段階論を考えてみよう。ラカンのいうように「鏡体験」のおかげで自己認識が成立するのではない。むしろ反対に、体感覚を通じた学習の結果、「鏡像認知」が可能になるのである。からだが先立つ。またラカンのいうように、ばらばらの身体興奮の集まりにすぎないいわば人間以前の存在が、鏡の中にまとまった像としての<わたし>を発見するのではない。すなわち「感覚同士が結びつく」のではなくて、「感覚同士ははじめから結びついている」。自分自身のからだと他人のからだをぶつけあって遊ぶことが、未分化の世界から分化した世界へと進む、決定的な足がかりとなる。身体感覚を通じて<わたし>を知ってはじめて、主体は鏡の中に<わたし>を発見することができるのだ。
さて、だからといって、ラカンの理論はまやかしだなどと言うつもりは毛頭ない。ラカンの理論はむしろ記号論的な意味で、すなわち<わたし>の内実は<他者>に私を重ね合わせることによってしか生まれてこないという意味で、また象徴が持つ役割を言説的に権威づける意味で、きわめて意義を持っているように思われる。<象徴界><対象a>は「使える」概念だ。だがしかし、発達論的な意味において、あるいはそもそもの人間の根源としてのカオスを考える上で、「鏡像段階論」に依拠しすぎることは少々危ういといわざるをえない。思想的に意味の地平を切り拓く上では有効であっても、それに基づいて実際に治療的介入を行うことには少々抵抗を感じてしまう。
セックスが根源的というのはこのような意味においてなのかもしれない。スキンシップこそが原初の私の感覚を与えてくれるものであるならば、肉体的な触れ合いにこそわたしは安らぎと戦慄を感じることができるだろう。ラカンの話にしろセックスの話にしろ、諸刃の剣をうまく振りかざしながら自分なりの意味体系を築いてゆきたいと強く感じた、6月1日。原宿駅にはもう紫陽花。
とっても心に染み入った内容だったので、ついコメントを・・。
2歳の子持ちのおばさんです。
「あなたが触れて、はじめてわたしが存在する」
難しいコメントは出来ませんが、子供を見ていると(特に男の子だからでしょうか?)母親とのスキンシップは、彼の中でとても大切な大切な時間であることが良くわかります。時にはうっとうしい事もありますが、「自分を確立している」のかと思うと、うっとうしいくらいが丁度いいのかもしれません。
とても面白いblogですね。今日、はじめて来ましたが、これからも読ませて頂きます。
音楽の趣味が私と似てらっしゃるので(アマチュアジャズバンドのマネージャーしてます)、そちらもこれからも楽しみに・・。
yumzouさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
子供と物理的に触れあうことが特に大切、
という実験結果は自分にとっても新鮮でした。
もっとも時にうっとうしくなるという気持ち、すごくわかります‥
上で紹介した『まなざしの誕生』という本は一般向けに書かれた本でもあるので、おすすめです。赤ちゃんがどのように世界を自分のものとしていくのかを心理学的に考えた上で、そこには育児のヒント、あるいは人間そのものを考える上でのきっかけがいっぱい詰まっていると思います。
アマチュアジャズバンドのマネージャーですか!自分はジャズピアノを挫折してしまいました。せっかくKeikoLeeにジャズを叩き込んだ人に教わっていたんですが、東京に来てしまったもので。素敵な演奏家たちをこれからも見守っていってくださいね。
もっともこのBlogは更新頻度が高くないので‥たまにまた訪れてやってください。それでは。
Posted by: Gen at June 3, 2004 02:21 AMふと図書館で、この文をよんで、ふわーっとした何かに抱きしめられたみたいな不思議な感覚を感じました。温かみのある素敵な文だと思いました。
Posted by: tomato-lover☆ at June 4, 2004 07:41 PMtomato-loverさん、どうも。
ふわーっと誰かに抱きしめられちゃってください。笑


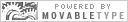
***→