・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
「日本人らしさ」は存在するのか?Vol.1 文化心理学を通じて
 私たちはよく「その考え方っていかにも日本人的だよな」「日本人って集団主義的だから俺には合わないんだよな」などと口にする。だがそもそも「日本人らしさ」って、一体何だ?以前のエントリーと重複しますが、丁寧に論じてみました。日本人は欧米人より集団に流されやすく、日本は村社会的だと感じてしまう人は、是非一度読んでみてください。
私たちはよく「その考え方っていかにも日本人的だよな」「日本人って集団主義的だから俺には合わないんだよな」などと口にする。だがそもそも「日本人らしさ」って、一体何だ?以前のエントリーと重複しますが、丁寧に論じてみました。日本人は欧米人より集団に流されやすく、日本は村社会的だと感じてしまう人は、是非一度読んでみてください。
一番普及している考え方は、西欧人は「個が確立しており、自己主張が強く、人の意見に流されにくい」、それに対し日本人は「個よりも和を尊び、集団主義的で、人に流されやすい」というものだろう。この考え方に沿って様々な書物が著されてきた。たとえばルース・ベネディクトの『菊と刀』が代表例だろう。またこの考え方は受験現代文・小論文の現場でも絶えず繰り返されており、学生を通じていまだに反復/再生産され続けている。
この文化による考え方の違いを、「文化による心性の違い」と捉え、心理学の領域で扱うことも可能になる(文化心理学)。日本で代表的なものとしては、京大の北山忍(とその一派)によるものがある。彼は、これまでの心理学は文化差による心性の違いを無視し、「個」としての心性を重視しすぎていたと批判する(これまでは心性単一性を仮定していたが、心性の潜在的多様性を仮定すべし!と)。彼によると、
「心理プロセスは文化の内容をなかに取り込むことにより成立し、それらに囲まれることにより維持され、同時に、文化の内容は心のプロセスの活動そのものを映し出している。つまり、心と文化は歴史的循環のなかで互いに生成しあうものである。(中略)この意味において、文化は実質的に心を作り上げており、また同時に、文化そのものも多くの心がより集まって働くことによって維持・変容されていく」(『文化心理学』)
ということになる。彼はこの考えに基づき、日本人は相互依存的自己観を持ち、欧米人は相互独立的自己観を持つと仮説を設定した。自己観とはすなわち、「自分が自分のことをどう見るか」ということである。この場合に即して言えば、日本人の相互依存的自己観とは、「自己とは他の人やまわりのことごとと結びついて高次の社会的ユニットの構成要素となる、本質的に関係志向的実体であるという自己についての文化的前提」であり、欧米人の相互独立的自己観とは、「自己とは他の人やまわりの事々とは区別され、切り離された実体であるという自己についての文化的前提」である。つまり簡単に言えば、日本人は自分を他者依存的な人間だと考えており、欧米人は自分を個人主義的な人間だと考えているということだ。彼はこのことを心理学的実験で実証した(心理学評論Vol43.No1を参照)。
彼の理論によれば、自己観は「行動・認知・感情」に影響を与えるという。ゆえに、そのような自己観を抱いた人々が構成する社会は、そのような自己観を反映するものになるという。つまり日本には相互協調的なものをよしとする文化慣習が芽生え、欧米には個人主義的なものをよしとする文化慣習が育つということだ。そのような文化慣習の中で育った人間は、今度は逆にそのような心性を身につけるだろう。すなわち日本人は集団主義的になり、欧米人は個人主義的になる。
考えてみよう。たしかに私たちは日本人は欧米人よりも集団主義的だと考えている。繰り返される言説、「日本人はムラ社会だ。村八分を思い出せ」「日本の会社はこれまで終身雇用をするなどいわば『日本株式会社』であった」「戦時中の軍国主義を生んだのは日本人の弱さである」などなど‥
だがこれに意義を唱えたのが東大の高野(とその一派)である。彼らが文化差に関する心理学的実験を洗い直しメタ分析を行ったところ、「日本人は欧米人より集団主義的だ」という結果は全く導かれなかった。彼らが実験を行っても同様の結果であった。すなわち「どちらかがより個人主義的で集団主義的だという結果は全く支持されなかった」(詳細はこちら)
では私たちは何故これほど「欧米人の方が個が確立している」と感じてしまうのか。その通説が生成/維持されるメカニズムは何なのか。
高野一派の説明によると、第1に「日本人の集団主義もアメリカ人の個人主義も、日本とアメリカがおかれていた歴史的状況によって説明が可能」だが、 私たちは状況的原因を人の性格に帰属させてしまいやすいバイアス(思考の歪み)を持っているからだという(これを「基本的帰属錯誤」という)。たとえば第二次世界大戦中の日本の軍国主義(全体主義)は日本人が持つ集団主義的傾向が原因といわれたりするけれども、それよりも「経済的・軍事的に追い詰められた国家は全体主義的傾向に向かう」という状況的な力の方が大きかったのではないか。第一次世界大戦の敗戦で貧困に追いやられたドイツはナチスという全体主義に走った。世界恐慌を経験したアメリカは、移民排斥という全体主義的傾向に向かった。冷戦時は、「赤狩り」などというとてつもない弾圧を行った。9.11以後のアメリカの言論統制の現状。どれをみても、「欧米人は自我が確立していて個人主義的だ。それに対して日本人は、他人に依存する集団主義的な性格を持つ。だから、第二次世界大戦時にあれだけの軍国主義に走ったのだ」なんてことは言えない。村社会の例にせよ、アメリカの実態を知っている者は、いかにアメリカも「村社会」であるか痛感しているだろう。
第2に、「性格の一貫性論争」(別称「人か状況か論争」)のなかで明らかになったように、固定的な「性格」が過大評価されがちであるものの、実際には、人間の行動・意識は状況の変化に対応してかなり柔軟に変化しうるものであることがあげられる。私たちは状況に応じて振る舞っており、「一貫した個人の性格」なんてものは、個人の行動に対し、一見思われているよりも微弱な影響しか及ぼさない。これは「自己」アイデンティティが「他者の他者」として成り立つことを考えても納得できる。これを「対応バイアス」というのだが、人間は状況の力を過小評価し、性格を過大評価する強い傾向を持っているのだ。
第3に、認知心理学で明らかにされた確証バイアス等によって、欧米人の誤った日本認識が強化された可能性が強いこと。「確証バイアス」とは、「自分がもっている仮説を確かめるときに、その仮説に合致する証拠を重視する傾向」を指す。わかりやすくいえば、自分が「こうだ!」と思ったら、その自分の考えと一致する証拠ばかりを探してしまい、それを否定するような証拠は見ないようにしてしまう思考の癖のことだ。以前に「第一印象と血液型の心理学」としてそのことを論じた(参照)。
欧米人は「自分たちは個が確立している」という自らのアイデンティティ(=自己規定)に誇りを持っているので、他の民族はそうではない(=集団主義的だ)というレッテルを貼りやすい。ゆえに、アジア(日本人)は集団主義的だという言説が絶えず欧米人によって繰り返されてきた。また、欧米の言説は学問の世界において特権的地位を占めている(サイードを想起するまでもなく)。したがって、欧米が生み出した「日本人=集団主義的、西欧人=個人主義的」という言説が力を持ち、その後は「確証バイアス」によってそれが強化されてきたのである。誰かの勇気ある個人主義的行動は「あの人は特別だよね」という言説によって退けられ、他人の意見に流された記憶だけが何度もリフレインされる。
このように「日本人=集団主義的、欧米人=個人主義的」という考え方は少なくとも絶対的に正しいものではなく、むしろ疑ってかかるべきものである。では、本当に「日本人」と「欧米人(特にアメリカ人)」の性格に違いはないのだろうか。いいかえれば、文化差は個人の性格とは無関係なのだろうか。全くそうとも言い切れないし、またこのような分析枠組み自体がそもそも限界を孕んでいるともいえる。そのことについては、次回に論じてみます。(この北山-高野論争の詳細は認知科学, 6, 106-114. に掲載されています)


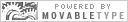
***→