・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
とりあえず究極の恋愛論part.2
 とりあえず究極の恋愛論part.1を先に読んでくださいませ。ヨゴレに徹して恋愛論を書いてます。
とりあえず究極の恋愛論part.1を先に読んでくださいませ。ヨゴレに徹して恋愛論を書いてます。
さて、今回は彼氏/彼女という「制度」について考えてみたい。いわば恋愛の制度論だ。言い換えれば、相手を好きということと、相手と付き合うということに違いはあるのか?セフレと恋人の違いは?
2. 制度としての恋愛論
彼氏/彼女ないし「恋人関係」がひとつの社会的制度であることに疑義を挟む人はいないだろう。現代は「恋愛至上主義社会」などと呼ばれたりする。興味ある方のみ次の引用部を読んでくださいませ。
家族形成の原理は、その歴史的展開において、まずは親子関係(血縁)を核にして形成されてきた。父系か母系かの差異はあっても、血縁によって家族は維持されていた。それが近代以前のことであり、その家族形態の拡張として国威発揚のイデオロギーが形成されていた。それが近代社会になると、親子関係に代わって、男女関係が優位になった。そのシンボルが恋愛関係である。血のつながりから、愛のつながりが優先される家族へと、家族(そして社会)形成の基本原則が変化した。だから近代社会における核家族は、まずは男女の恋愛から形成されなければならない。愛の絆は血の絆を超えるものになった。今のハリウッド映画で執拗なまでに恋愛の価値が高揚されているのは、このような社会的な背景と無関係ではない。わたしたちは無意識に恋愛至上主義のイデオロギーに浸り、これこそが人間らしいあり方だ、と信じている。つまり核家族では、愛がすべての本質である。それを無視して核家族は成立しない。ほんの少し前までは、誰もが血縁によるイエの継承こそが家族(伝統的家族)のあるべき姿だ、と信じていたのに、今では、誰もが「愛がすべてだ」と信じきっている。(熊坂賢次の仕事場より)
前回指摘したとおり、二人の愛は、a. 性的かつ b. かけがえのない自分のアイデンティティを相互に構築しあうという面を持っている。これは恋愛至上主義ではない。源氏物語やクレオパトラにまつわる逸話を紐解くまでもなく、恋ないし愛は悠久の時から長らく存在してきた。恋愛至上主義とは、社会的に恋愛が至上の価値を持つ、あるいはそのことが許される言説が流布する状態である。二人の愛に至上の価値が置かれる言説が流布する社会では(ex.映画、小説、j-pop、友人との「最近どーなのよ?」トークetc...)、恋愛することが脅迫観念的に必要なこととなる。わたしたちは「恋愛せねばならない」という圧迫を常に感じ、童貞/処女が必要以上に恥ずべきこととされ、手をつないで歩く街の恋人たちに自意識過剰的なまなざしを向けることになる。
二人の愛の感情は前回指摘したとおりa. b. 両方から生じている。どちらも<わたし>を満たしてくれる。したがって別に社会が恋愛至上主義でなくとも、愛は魅惑的な果実となるだろう。だがしかし恋愛至上主義社会になることによって、「恋愛してなきゃダメだよね」「つーか恋人いないとかありえない」「マジ寂しいんだけど」みたく、恋愛をしていないという事実が否定的に扱われるようになるのだ。非-恋愛にまつわる事柄はネガティブな価値を帯びるようになる、これこそが恋愛至上主義社会の特質である。恋愛マンセーの価値観と相容れないものは頭ごなしに排除されるのだ。そしてマンセーされた恋愛の社会的価値と先述したa. b. の三つが循環的に作用しあい、「とりあえず基本的に恋愛がすべてだし」という状態が暗黙のうちに仮定されることになる。
さらに現代は「彼氏/彼女=恋人関係」のみならず、「愛=エロス」そのものにことさら価値が置かれる社会であるという気もする。付き合っていなくとも好きならば体を許す、「セフレ」。かつては秘匿すべきこととされた関係が、「好きなら良くね?」「エロくて素敵だね」という言葉のもとに社会的に受容されつつある。プータローが「フリーター」という言葉を獲得しネガティヴなイメージから多少解放されたように、「セフレ=体の関係=友達以上恋人未満」という言葉は、それをひとつの社会的に許された在り方として描き出す働きを持っている。とはいえもちろん、彼氏/彼女関係こそが社会的にもっとも憧れ/目指すべきものとされていることも事実であり、セフレは例外的オプションとして周縁に追いやられ、中心はやはり恋人関係が占めているともいえるのだが。
ところで面白いことに、社会的に恋愛(セックス)が公認されるにつれ、恋愛はつまらなくなっているともいえるだろう。タブーが失われると恋愛の「禁断の果実」性が減少し、ドキドキが少なくなる。「駆け落ち」の時代に生まれてみたかった。「心中」という言葉を発してみたかった。恋愛関係が必要以上に認められることによって、恋愛は凡庸になる。したがって(刺激を求めて)次々新たな恋人に乗り換えてゆく「今まで何人とつきあいましたか?」の時代が到来する。セフレがポジティブなイメージを獲得しつつあるのは、このことと無関係ではないだろう。人はタブーを求める。タブーは食い尽くされ消費されてゆく。次は兄妹の関係が認められる時代だろうか?あるいは不倫が新たなポジティブなイメージを持つ言葉を獲得する時代だろうか?
では「付き合う」とは何か。ここからは少々自分の体験をふまえた暴露的な論考になるが、厭わず書いてゆきたい。自分の恋愛はセックスが付き合うことに先行する場合が多いなどとは口が裂けても言えないのだが、そうだとするならば、私にとって「付き合う」と何が変わるのだろうか。
何よりも独占欲が満たされる。わたしにはあなただけ/あなたにはわたしだけ。他の奴とはセックスをするな。オレを一番大切にしろ。排他的なパートナーシップを形成することは適応上(子孫を繁栄させる上では)有利という進化論的な面もあるだろう。これはa. の性的なものに関連する。あるいは前回書いたとおり「あなたにはわたしだけ」だからこそ「わたしにはあなただけ」となるわけで、すなわち唯一性がかけがえのない<わたし>のアイデンティティを与えてくれる(これはb. の面)。みんなにモテるあの人と付き合いたい(=独占したい)。
このようにa. b. 両方の面から激しい独占欲と嫉妬心が生まれるが、付き合うということ、つまり彼氏/彼女という制度は、独占欲を満たし嫉妬心を抑える効果的な社会契約なのである。そして恋愛至上主義社会のさまざまな言説も、彼氏/彼女という契約を結んだわたしたちを褒め讃えてくれるだろう。
結婚=はじめて二人がセックスするという時代は終焉を迎え、恋人でなければセックスしちゃいけない時代でもなくなりつつある今、結婚するまでの自由な時間にそれでもあえて付き合うということは、a.の性欲よりもb.の「独占したい=かけがえのない<わたし>を与えて!」という叫びの方が強いことを示唆しているのかもしれない。


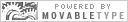
***→