・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
偶有性――他者を想う可能性
 昨日の記事で扱った「偶有性」という概念が、小さな頃から考えてきたことを端的にあらわしていると気づいたので、とりとめもなく、メモしておこうと思った。
昨日の記事で扱った「偶有性」という概念が、小さな頃から考えてきたことを端的にあらわしていると気づいたので、とりとめもなく、メモしておこうと思った。
偶有性(contingency)とは、「AではなくBでもありえた/BでもありえたのにAである」こと、つまり「可能だが必然でもない/必然ではないが不可能でもない」ことだった。なにも難しい言葉を使わなくても、たとえば「運が悪い」ってのも偶有性の問題だ。論理的必然性、および明確な因果関係は無い、けれどもなぜか自分が被害者に選ばれてしまった、ということ。たとえば、運転士の速度超過など、脱線事故に必然性があったとしても、わたしの恋人が犠牲者になる必然性は存在しなかった。わたしの恋人が命を落としたのは、偶有性の問題だ。
昨日書いたことを繰り返すが、偶有性は必然性(因果関係)ではないので、それに責任を求めることは出来ない。「たまたまわたしの恋人が地震で亡くなった」という偶有性の責任を取ってくれる者などどこにもいない。「運が悪かった」としかいいようがない。やるせない。やるせない状態は、耐え難い。だから、たとえば「耐震性の弱い木造建築を放置していた行政の責任だ!人災だ!」などと思いたくもなる。
人は、因果関係の無い出来事にひどく怯える。偶有性の問題を、あたかも因果関係のある必然性の問題であるかのように偽装する。そのために、仏教で言うところの「因果応報」や「業」という概念が開発されたのだろう。「バチ」が当たる、とか。「運」という言葉も、偶有性の問題を必然性の装いでカモフラージュする。宗教とは、偶有性を巧みに扱う技法である。そんな感想を、最近抱いている。
けれども、逆にいえば、宗教は偶有性をポジティブな意味で扱っているともいえるだろう。たとえば貧しくて苦しんでいる人が目の前にいる。この貧しさが偶有性の問題だとすれば、「わたしが彼の立場でもありえた」ことになる。ここに平等愛が芽生える。合理性・因果関係の世界に生きている私たちからすれば、「おまえが仕事を怠けただけだろ」となってしまうのだが。つまり、必然性を導入しない限り、ある他者を断罪する(=自分から切り離す)ことはできない。必然性ないし理由を見い出す営みは、自分から対象を切り離すことでもある。マザー・テレサは、生涯、身を切るような偶有性に取り憑かれていたのだろう。
霊や呪術や民間療法といったものも、ある意味では、偶有性を必然性に偽装するためにおそらく開発された。科学の一部は、偶有性を必然性に(偽装ではなく)「変換」するが、そうであるがゆえに、わたしたちは科学が大好きだ。
私たちが不幸な境遇に陥っている他者と接する際に、偶有性の意識に貫かれてコミュニケーションをとるならば、それは「共感(=sympathy ; 共にある感情)」となるだろう。でも、他者が(理由があって)必然性から不幸な境遇に陥ったと考えるならば、それは「憐れみ(=pity ; 自分から他者を切り離した状態)」となるだろう。
先日、津波で数十万人が亡くなった。わたしは言葉を失った。おそらく偶有性を感じていたのだろう。偶有性(=わたしが彼らであり得たかもしれないという感覚)に打ちのめされたとき、人はおそらく言葉を無くす。だが、偶有性の感覚こそが倫理の可能性だとわたしは感じている。偶有性は共感を生む。共感が、人の根源的な愛を生む。
「自業自得」という言葉がある。たとえ必然性からある人が不幸な境遇に陥ったのではなくても、わたしたちは「業」という偶有性を必然性に偽装する言葉を用いて、彼をわたしたちから切り離す。逆にいえば、悲惨な状況に陥った人々を目の前にし動揺するとき、わたしたちは何らかの偶有性を感じている。自分の心が痛むとは、偶有性を感じることである。「彼ではなく私でもありえた/私でもありえたのに彼である」と感じる可能性。「愛」という空疎な言葉をひとまず措いておくとすれば、倫理の可能性はここにしかないのではないか。
ある事故が生じる。もちろん原因追及は必要だ。原因追及の営みが、人類に進歩をもたらした。昨日のリスク論に書いたとおり、原因追及は、私情を挟まずシビアに/科学的に行うべきである。だが、原因追及がもたらす必然性の感覚は、わたしを他者から切断してしまう。「彼ではなく私でもありえた/私でもありえたのに彼である」ことを覆い隠してしまう。「共感」が「憐れみ」になってしまう。現代が「心貧しい時代である」といわれるならば、このことが一因でもあるだろう。
たとえば世界中で戦争に苦しむ人々を想うとき、「戦争反対!」のスローガンはあまり役立たない。冷静に、アメリカや中国を中心として繰り広げられるパワーポリティクスを見極める必要がある。因果関係(必然性)の推定は、科学的、冷徹に行わねばなるまい。だが、「必然性」の感覚に支配されて、苦しむ人々から自らを切断してしまうのは違う。この科学の時代にあって、どこまで自分の中に「偶有性」の感覚――他者を想う可能性――を保てるのか。一人の人間として、常に問われている。
※大澤真幸さんが扱っている社会学的な「偶有性」の概念はあまり追ったことがないので、心優しい方がいらっしゃるならば、「おいおい」ってところを指摘してくださると望外の喜びです。
Posted by: Gen at April 28, 2005 04:24 AM「遇有性」なる言葉をはじめて聴きました。
ただ、私自身は、理系(?)の立場から、「交換可能性・不可能性」という言葉で、(おそらく)同種の問題を考察しております。
「わたし」と「あなた」の「交換可能性」こそが、「こころ・情」を「科学的・客観的」に扱いうるかどうかという(境界)問題(私は主観的・客観的という区分は厳密には不可能だと思っています)に該当すると思っています。
きすぎじねんさん、コメントありがとうございます。
>「わたし」と「あなた」の「交換可能性」こそが、「こころ・情」を「科学的・客観的」に扱いうるかどうかという(境界)問題に該当すると思っています。
その場合、<交換可能なもの=科学的に扱いうるもの/交換不可能なもの=科学的に扱いえないもの>という図式になるのでしょうか。
わたしは、交換可能性が倫理の可能性だと考えています。きすぎじねんさんの図式と食い違うのは、交換可能性の対概念に何を置くかが異なるからなのでしょうね。
「交換不可能なもの=個人の内面に関するもの」と考えるか、「交換不可能なもの=(科学的・論理的)必然性に関するもの」と考えるかの違いでしょう。
面白いのは、(交換不可能な)「主観」的には、きすぎさんのいう「交換不可能なもの」ですら「交換可能なもの」に思えてしまうところではないでしょうか。
なるほど。。。倫理の問題ですか。。。
私の場合、たとえば「交換可能なもの→不可能なもの」へと思考を進めてきているため、そういった問題を一側面から見てしまうのかもしれないですね。。。
遇有性とは、逆に「不可能なもの→可能なもの」という方向性から見ていくように思われます。
両者の境界は一本の線ではなく揺れ動く幅を持ちながら重なり合うと思います。
そういう意味で、
> 面白いのは、(交換不可能な)「主観」的には、きすぎさんのいう「交換不可能なもの」ですら「交換可能なもの」に思えてしまうところではないでしょうか。
ということが浮かび上がってくるんだろうと思います。
このあたりの2方向の考え方の交錯は、ユングとパウリとが共著した「自然現象と心の構造―非因果的連関の原理」に重なるところが大きいようにも思われます。
http://jinen.exblog.jp/m2004-12-01/#1320594


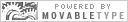
***→