・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
リスクを抱えて生きる――確率と偶有性
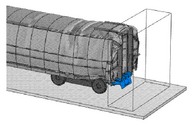 先日のJR事故ニュースに関連して思ったことを、いくつか。第1に、JR側に100パーセント責任を負わせることができるかどうかについて、法的な論理を離れて、いささか抽象的に考えてみる。第2に、確率としてのリスクと、まさに他ならないわたしが被害者になるということの間にある埋めがたい距離について(偶有性=contingency)。反論を切実に希望します。 ※04/27, 16:00, 後半大幅加筆修正
先日のJR事故ニュースに関連して思ったことを、いくつか。第1に、JR側に100パーセント責任を負わせることができるかどうかについて、法的な論理を離れて、いささか抽象的に考えてみる。第2に、確率としてのリスクと、まさに他ならないわたしが被害者になるということの間にある埋めがたい距離について(偶有性=contingency)。反論を切実に希望します。 ※04/27, 16:00, 後半大幅加筆修正
第1に、JRをただ非難するのはおかしいよ、という話から。ここ数年はリスク論やリスク学が大流行しており、文1東大後期小論文の問題まで『安全学』から出題される有様だったのだが、事故などの「リスクを0に抑える」ことが至上命題だと勘違いしてはならないだろう。リスクを可能な限り抑えることが大切なのだ。第1に、何をとっても100%の安全などあり得ない。第2に、リスクコントロールするためには人的・物的資源が必要だが、それらは有限である。あるシステムのリスクと、それを減らすために必要なコストを天秤にかけて、妥協点(均衡点)を探すほかない。「可能な限り」とは、「リスクコントロールにかかるコストの許す限り」、という意味だ。BSE問題(全頭検査)にしろ、原子力発電所の問題にしろ。
なぜわたしたちは、時速を100km近くも出す、危険なシステム(鉄道システム)の存在を許しているのだろう。便利だからだ。必要だからだ。つまり、社会でせめぎ合っているのは、1.システムの有用性、2.システムが孕むリスク、3.システムのリスクをコントロールするために生じるコスト、これら三点であろう。(註:もちろん、「システム構築にかかるコスト」も大事なファクターだが、ひとまず措いておく)
鉄道システムは必ずリスクを孕んでいる。だが、便利なので、存続させざるをえない。鉄道システムを存続させることに、わたしたちは同意している(=リスクを引き受ける宣言をしている)。そこで、なるべくリスクをコントロールしようと、様々な安全装置が開発されてきた。だが、安全装置の開発や運転士の教育へ、無尽蔵な資金を投入することは出来ない。事故の責任が必ずシステム設計者側(JR)にあるとするならば、「東京駅から渋谷駅までの運賃が1万円」になることをわたしたちは覚悟せねばなるまい。
つまり、わたしたち自身が「安い運賃」「利便性」と引き替えに、ある程度のリスクを承認しているのだ。このことを忘れてJRを糾弾するのは、褒められたものではない。原子力発電所と来るべき東海大地震の問題にせよ、問われているのは、「わたしたちが何と引き替えに何を失うのか」であって、行政側をただ糾弾すれば済む話ではない。何よりも、「どのような社会を築くのか」というヴィジョンを巡って論争がなされるべきだろう。BSE問題も、わたしたちが「牛肉100グラム=2万円」に耐えられないとすれば、どこかで妥協するほかない。「肉を食わない」のが手っ取り早い。食肉がハイリスクな営みであることを、多くの学者が明らかにしてきた。ちなみに、この問題に関心がある人には『環境リスク学』を推奨したい。わたしたちは様々な恩恵を被るかわりに、はじめからリスクをある程度は引き受けている。問われているのは、「どのような社会を築くのか」というヴィジョンである。このことは胸に刻んでおきたい。
もちろん、被害者やご遺族の方々が、「他の平均的な水準と比較して○○の点でJRに落ち度があった。だから賠償しろ」と要求することは、理にかなっている。また、再発防止(=リスクコントロール)のため、JR側が何らかの対策を講じる必要もあるだろう。100%の安全を目指すものではないが、今まで以上に、リスクコントロールへコストをかけるということだ。均衡点をずらすこと。大事故が起きるたび、わたしたちはある程度のコストを支払うことに同意し、リスクコントロールは精度を増してきた。たとえば、9.11事件が生じ、セキュリティーチェックのため長時間待たされるようになったが、わたしたちはおおむね納得している。リスクとコストをめぐる言説を追跡する社会科学者の仕事も重要だろう。
長くなってしまった。第2の論点に移ろう。リスク論は政策科学なので、確率として事故を扱う。誰が亡くなったのかは問題ではなく、事故は確率の問題として処理される。たとえば、野蛮な話だが、10万回に一回の事故を防ぐために100億円かけるよりは、その一回きりの事故の被害者に対し1億円払った方が良いわけだ。「必然性」の問題を扱う哲学に対して、不確実な・確率的な世界を扱うベイズ認識論のようなものともいえるだろう。
だが、わたしは他ならないわたしである。「なぜ10万分の1の確率を、よりによって、わたしの夫が引き受けねばならなかったのか」、と。これが偶有性(contingency)に関連する問題だ。偶有性とは、「AではなくBでもありえた/BでもありえたのにAである」ということ、つまり「可能だが必然でもない/必然ではないが不可能でもない」ことである。夫が脱線事故に巻き込まれたのは必然ではない。だが、現に巻き込まれてしまった。犠牲者はわたしでもあり得た。他の人でもあり得た。でも、現に夫が亡くなってしまったのだ。
この不条理の穴に落ちてしまった犠牲者・ご遺族の方々の痛みは、心底、尊重すべきだと思う。「システムの確率の問題なんだ。運が悪かった。賠償する」だけで済まされない何かを、彼(女)らは抱えてしまった。これは圧倒的で決定的なことだ。社会として、そして一個人としても、この「痛み」に対する配慮の感受性だけは失ってはならないと感じる。その意味で、被害者・ご遺族の方々は、JRに恨みのありったけをぶつける権利を持っていると思う。二重の意味での「偶有性」を見据えたい。ひとつは、(他の誰でもなく)彼が選ばれてしまったことの圧倒的な痛み。もうひとつは、(彼ではなく)自分が選ばれていた可能性も全くあり得ること。
もう一度、あなたの恋人が今回の事故で亡くなったと想定して欲しい。あなたは何に嘆くだろうか。わたしならば、<なぜよりによって私の恋人が死ななければならなかったのか>と考える。偶有性こそを呪う。だが、偶有性は、いかなる責任も引き受けてはくれない。「私の恋人ではなく他者でもありえた/他者でもありえたのに私の恋人である」という話なのだから。そこで、遺族であるわたしは、確たる事故原因(=必然性)を探し求め、JRを糾弾し始めるだろう。死の必然的理由を見つけるために。どこまで責めても、まったく返事のない、偶有性の痛みから逃れるために。このこと自体は尊重しなければならないと、わたしは思うのだ。
とはいえ、わたしたちは冷静にならねばならない。自分を100%棚に上げて行政やJRを非難する権利など有していない。まずは冷静に事故調査委員会の報告を待つこと。そして、「自らリスクを引き受けて生きている」自覚を持つこと。あるシステムのリスクは、単純に行政側の問題ではなく、わたしたちがどう生きるか/どのような社会を築くか、と不可分だと知ること。おそらくは。
「偶有性」の穴が、裂け目のように、あなたの隣でぱっくり口を開いている。わずかな事故の確率の中で、他ならぬ<あなた>が選ばれてしまったことに、責任を取れる者はいない。「偶有性」という裂け目のいたずらなのだから。生は死に含まれている。その上で、「列車脱線事故・・・安全なのは何両目か?」という記事も参考にしてみて欲しい。
批判ではないのですが、疑問があります。Genさんは、「JRを利用することは、それがもたらすリスクを引き受けた上で利用すべきだ」という風に主張しているように私は読み取りました。(読み取りが間違っていたらすみません。)
しかし、その主張の後で、『もちろん、被害者やご遺族の方々が、「他の平均的な水準と比較して○○の点でJRに落ち度があった。だから賠償しろ」と要求することは、理にかなっている』と述べているのですが、なぜ遺族は要求できるとお考えですか?ほかのひととの違いはなんなんでしょうか?
名前を書き忘れました。失礼しました。
Posted by: tomato-lover at May 2, 2005 12:41 AMExcerpt: 「食品に関するリスクコミュニケーション(米国産牛肉等のリスク管理措置に関する意見交換会)」の開催(5月20日) http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20050427press_6.html 参加してきました。急ぎにつき雑文で申し訳ありませんが、いくつかトピックをご報告します...
From: BSE&食と感染症 つぶやきブログ
Date: 2005.05.22


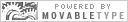
***→