・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
「言葉が生まれるべき場所」を探して―――其の1
自分の言葉の根拠はなにか?たとえばこうしてBlogを書くけれども、その言葉はどこから生まれてきたのか?ざっと考えつく限りでは
1.本や他のHPなど以前に読んだテクスト
2.生きる上での純粋な自分の人生経験
3.芸術などの感性を豊かにし言葉を触発するもの
「情報理論」なるものでは、ある情報の価値は、a.確実性、b.意外性が規定しているらしい。a.確実性とは、情報の確かさ。噂話よりは、論文に書かれていることのほうが信憑性が高く、情報価値が高い。b.意外性とは、情報の目新しさ・独創性。どこかで聞いた話は2度も聞きたくないわけです。
たとえば俺がAV女優だったら、おそらく仕事の話をするだけで読者はついてくる。2.の人生経験の情報価値が高いためです。でもしがない大学生としては、自分自身で、なにか言葉が生まれてくる場所を創り出すしかない。しかもGenは人文系の学者=言葉で飯を食ってこうとしている。どこから言葉を産み出そうか、と常々悩んでしまう。では、言葉はどこから生まれてくるのか?

実は2.の人生経験や3.の芸術体験も、それ自体では経験/体験した個人の内部にとどまってしまう。言葉にしてはじめて、他者に伝わる。「言葉にする」とは、その経験/体験を、自分が解釈するということ。「解釈する」には、自分自身の価値観が必要となる。じゃあ、その自分自身の価値観が生まれる場所は、どこ?
まず、1.の読書経験なんかが大きく絡んでくる。でも何を読むかを決めるのは、自分自身の2.経験だったりする。本を読むより先に、まず自分には生きてきたという歴史がある。そして3.の芸術経験も、2.の人生経験のあるひとつの側面だ。つまり、1と2と3は循環的に作用しあっている。
純粋に自分自身は、新しい価値のある情報=言葉を生み出せるのだろうか。その言葉の根拠となる場所を、どこに定めようか。これは本当に切実な問題。しかも学者を目指すGenにとってはなおさら。たとえば旅をして旅行記を書いてみた。たとえば読書して論文を書いてみた。いつも襲われる不安と虚しさは、「ホントに俺がこんなこと語ってて意味があるの?この言葉に価値はあるの?誰かの言葉を再生産してるだけじゃん?誰も楽しんでないんじゃん?」という自分への問いかけなわけです。
その「言葉が生まれるべき場所」を捜し求めて、生きているような気がする。色々と旅をしてきたのもそのためかもしれない。Genは今後、具体的には心理学的な臨床の現場やフィールドワークにそれを求めようとしている。あるいは友達は演劇や音楽に、あるいは後輩は哲学書に、それを求めようとしている。その場所が、心の底から、欲しい。それも、個人的には、本とかじゃなく、もっと身体的に根拠のある、「言葉が生まれるべき場所」が欲しい。たとえそれが幻想に過ぎなくても、肉体感覚、身体感覚から言葉を発したい。「確実性」と「意外性」を常に意識しながら。
それってつまり、「俺(私)にはこれがあるから大丈夫」って感覚なんですよね。きっと。生きてるアイデンティティというか。でも不思議なのは、Blogとかだと、書いている内容そのものよりも、その人そのもの、つまりその書き手の魅力や人柄が評価されているような気がして。このことはもっと掘り下げて、考え、書いていこうと思う。でも一体どんなときに、このBlogを読んでる人は「面白い!」と感じているんだろう‥


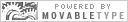
***→