・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
『必読書150』
イラクの歴史とか民間活動についてとか書きたいことは山ほどあるのですが、さすがに週末にまわします。さて、柄谷行人とか浅田彰といったまぁそっち系の方々が集まって書いた『必読書150』という本があります。キャッチコピーは「これを読まなければサルである」と挑発的。で、偶然にもその読書リストで何があげられているかを掲載しているBlogを発見(shuのつれづれなるままにさん)。あなたはどれくらい読みましたか?
必読書150
柄谷 行人, 岡崎 乾二郎, 島田 雅彦, 渡部 直己, 浅田 彰, 奥泉 光, スガ 秀実
ひとこと。ここに挙げられている本は、日常世界を根底から動揺させる意欲と強さに満ちた珠玉のテクストだとは思うけれども、その種の教養は好きな人がまとえば良いのであって、オルタナティブな教養も確実にあるし、まずそれが重要だと思う。どうしても職人さんが頭の隅から離れなくて。でも、この150冊で考えたものを自分の身体感覚と統合させられれば深い人間になれるはず(4年以内に全部読もう)。またとにかく、「無知の知」「不可知の知」をもたらしてくれるという意味では、素晴らしい。以下、参考までに。
The Consolation of Philosophy: No. 6「この世界において、自分にはわからないことは何もない」とついつい言いたくなりますが、人間に確実に知ることのできることとそうでないことを区別し、人間にとって重要な事柄から優先して知るようにしようという謙虚かつ実用的な態度は、われわれの日常生活でも重要ですし、現代科学に何ができるかという問いについて考えるときにも重要になってくると思います。「知らないことを知っている」というソクラテス流の「無知の知」と同様に、「何を知ることができないかを知っている」というロック流のいわば「不可知の知」もわれわれが生きる上で大切な知見だと言えるでしょう。
はじめまして。
ポン!と辿り着いて見たその先で、面白いサイトではないかと思ったら、自分のブログをBlog Peopleでリンクして頂いていたので二重に驚きでした。まだGenさんの膨大で濃い記事を全て閲覧できていませんが、これから巡回させて頂きます・
なお、文化人類学に専攻を決められたのこと。正直心理学と人類学とどちらが良いのか判断する術なぞ門外漢たる拙者にはありませんが、人類学なら僕も関連領域ですし、リアルワールドで会う事もあるかも知れません、その際はヨロシクお願いします。
mowさん、はじめまして。
こちらこそいつも刺激的に読ませていただいてます。
イラク問題への視点や、『「常識」という罠』というエントリーも、思わず頷いてしまいました。
ただ、このBlogは論理性を無視して感情的に書いている面が強いので、
あまり参考にならないかもしれません。
いわば、学問的なwritingが現実感覚から乖離しすぎないように、
このBlogでバランスを取っている感じです。
また強度ある文章を楽しみにしています。
研究会にも色々顔を出しているので、近いうちにリアルワールドでクロスするかもしれませんね。
色々な意味で、これからもよろしくお願いします。
Excerpt: 今日、息抜きがてらに書店に立ち寄った際に、おもむろに手に取ったのが『柄谷行人ほか著「必読書150」太田出版』であった。以前からこの本の存在自体は知ってはいたのだが、実際に手に取ったのは初めてであった。 少しパラパラとめくってみると衝撃的なフレーズが目に
From: yasuchan's blog
Date: 2005.04.29


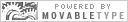

***→