・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
罫線つきノートやBlogは思考の仕方を強制する
 ここ最近ポータル構築ツールのXoopsや情報集積ツールのPukiwikiなんかをサーバーに入れて試して遊んでました。色々なネットツールを弄んで感じるのはやっぱ、技術が人の思考や表現の仕方を大きく規定しているということ。
ここ最近ポータル構築ツールのXoopsや情報集積ツールのPukiwikiなんかをサーバーに入れて試して遊んでました。色々なネットツールを弄んで感じるのはやっぱ、技術が人の思考や表現の仕方を大きく規定しているということ。
このBlogだって、昔からサイトに訪れて下さった方はわかると思うけれども、Genの思考様式を大きく規定している。どこかからソースや商品や写真をひっぱってきて、それにコメントを付け加える。あるいは自分がBlog村の一員であることを自覚して、メタブログ的(ブログについて)話を書いてみたり。様式に染まった思考に行き詰って、更新が滞っています。初心に帰ろう。
面白い友達がいます。彼は講義を受けるとき、絶対に罫線つきの普通のノートを使わない。あくまで落書き帳みたいな、全くの白紙のメモを用いる。そこに書き殴る。「何でそんなもの使うんだ?」と聞いてみた、彼曰く、「罫線つきのノートは、罫線によって自分の考えが区切られ強制されるだろ?どの大きさで文字を書くか、どこに書くか、どんな順序で配置するか、それによってぜんぜん変わってくるんだよ?」。
「おっ」と思った。たしかに罫線つきのノートは、かなり書き方を強制する。それゆえに、読み返したとき、見やすい綺麗なノートができあがる。でもそれは、表現形式をノートによって強制されているからこそまとまったものができあがる、ということ。たまたま貰った手帳の記入欄が広ければ、おそらくちょっとは日記風の手帳ができあがる。狭ければ、淡々とした予定帳が完成する。パワーポイントの普及はプレゼンテーションの仕方を均一化した。
あるいはそれは書き手だけではなく、読み手にもいえること。だからこそ、本当に気持ちのこもった文章はEmailで受け取りたくない。できれば媒体(カードや紙など)を選ぶ段階から、どの大きさ、どんなレイアウトで文字を書くのかということも含めて、考えつくして渡してほしい。
自分がどんなツールを用いて表現しているのかということに、より敏感になろう。考えるときに使っているものが、実は裏で考え方を支配している。徹底的にこだわろう。そんな決意をあらたにした、この一週間でした。
必要に応じて罫線なんか気にしないで書けば良いだけでは。
Posted by: Atsushi_009 at March 8, 2004 12:26 AMコメントありがとうございます。
いや、普段どんなツールを用いて記録取るかを考えずに、なんとなく罫線を用いたノートなんかを使ってる自分に気づいた、というお話です。ふつう講義録なんかを取るときには罫線ノートが一般的ですよね?でも、それを用いるということは、一定の枠に自分を押し込めているということなんだと「自覚」しながら、その上でツールを自分なりに選んでいこう、という。
用いているツールをとことん自覚するのって、結構難しいんじゃないか、と思うんですけども。でも、その指摘はたしかにすべてだと思いますね。
Posted by: Gen at March 8, 2004 12:33 AM僕は完全にA型気質なので、罫線があると必ずそれに沿って書いてしまいます。
でも、ノートに色ペンを使用するのも面倒で、どの単語が大事だったのか忘れますね。
そういえば一度罫線なしのノートを使用したら、自分なりに図を使ったりしてとてもグラフィカルでわかりやすいノートになりました。(まあ、自分以外の人が見たらただの落書きですが・・・)
よし、これから罫線なしのノートを買いに行きます。
Posted by: けんじ at March 8, 2004 09:16 AMはじめまして。コメントありがとうございます。
自分なりのスタイルを模索するためにあれこれ努力してみるのって、悪くないですよね。より柔軟になるために、多少面倒くさいことも厭わず引き受けなければ、と最近特に考えたりします。
Posted by: Gen at March 9, 2004 08:19 PMはじめまして。高校時代までノートを取る習慣がなかったので、いまもメモをとるときなどは罫線などは無視してかきなぐってしまいます。反面、パワーポイントやワープロソフトを使うようになってからは、思考の枠組みがそれに制限されたような気がします。ツールの制約性って、想定された使い方をどこまで勝手に踏み越えられるのかということによっても変わってくるような気がしました(紙のノートは罫線を無視できるが、パワーポイントはスライドを単位とすることを無視できない)。なんだかまとまりがありませんが。ではでは。
Posted by: ebony at May 12, 2004 11:12 AMebonyさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
そう感じます。テクノロジー的にしっかりしてくればくるほど、行動の可能性は逆に狭められてしまう部分がありますよね。
パワーポイントでスライド一枚に一文字づつ、などという用い方をするとそれはもはやアートの領域に入ってしまうような気がします。
用いているツールの規約性に自覚的であること、あるいは多様なツールを試してみること。これくらいしか、できることはないのかもしれませんね。
Posted by: Gen at May 15, 2004 02:34 PMブログのインターフェースに「思考の仕方を強制」されてるとは思わないなぁ。
表現方法に制限があるだけでは?
箱男さん、はじめまして。
表現方法に制限があること自体、表現の根底にある思考を(ある程度は)規定してしまっているのだ、と私は考えています。さながら、小説や哲学で文体そのものが思考を照射するものであるように。
まぁコレは個人的な感覚の問題でもあるんでしょうが、hatenaを使うのかmoveble-typeを使うのかあるいはhtml1ページの日記を書くのかで、結構変わってきます。書き方が。そして書き方が変わるということは、私の感覚では、思考の仕方そのものがある程度変わるということです。
もちろん各ツールに付随している社会的な約束事が大きいのでしょうが。書き手は読み手を想定しながら書くので。
Posted by: Gen at January 15, 2005 05:22 PM罫線の功罪、確かにあります、私にとっても。
なるべくうすいものか、クロッキーブックのようなものが気が楽です。
書く位置、順番も重要ですよね。いわば脳の視覚化の場となるわけですから、いろいろ試行錯誤してみると思わぬ発想が生まれるかも・・
と、CD型のグリーティングカードに中心からぐるぐるとかきつづって見たことがあります。(息切れしました)
文の構築性を得られそうな気がして普通の横書きを下から書いたらどうかなともやってみました。日本では縦書きをする際に右手の小指の汚れは文化として厭わないので横書きを下からするのも許容範囲のはず、・
でやってみるとなんだか自発的に出てきた言葉のようで愛着がわきます。
葵さん、どうもコメントありがとうございます。
>いわば脳の視覚化の場となるわけですから
まさにこれですよね。人間は環境にある様々な道具を、脳の延長物として利用している。
音楽でも、A面B面というレコード文化から、80min程度のCD文化に移行したことによって、決定的に何かが変わったような気がします。
個人的に欲しいのは、自分が喋った言葉をリアルタイムで文章化してくれるソフトですね。まぁどの漢字を当てはめればよいのかの判断が難しく、なかなか完成されない技術なのでしょうが。行きつ戻りつの思考の軌跡をじっくりと吟味してみたいという思いがあります。
Posted by: Gen at January 21, 2005 02:57 AMExcerpt: Genxx.blog* : 罫線つきノートやBlogは思考の仕方を強制する
From: philosophical
Date: 2004.03.08
Excerpt: PowerPointって使いづらい。 最近、仕事でPowerPointでの発表資料を作っているのですけれども… 非常に使いづらい気がして…。 どうにも上手く作れなくて、「プレゼンテーション 用い方」とかってぐぐってみたら トラックバックしてるブログに行き着いたり。 このブログの...
From: ツレヅレ ブログ
Date: 2005.04.26


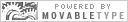
***→