・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
成人の日に思う
 たまには雑談を。2年前、あの日をそれとなく想い出す。今年慶應の哲学科から毎日新聞に就職する小学校の同級生と、東海道線の普通列車を乗り継ぎ名古屋へ向かった。ぬるいビールの喉ごしと、浮ついた夢や少しばかりの諦念が混じった近況報告と、もはや昔のような距離には近づけない寂しさと、車窓から見える薄ぼけた赤色に染まる富士山を背に釣りを楽しむおっちゃん達の横顔が、感覚として残っている。
たまには雑談を。2年前、あの日をそれとなく想い出す。今年慶應の哲学科から毎日新聞に就職する小学校の同級生と、東海道線の普通列車を乗り継ぎ名古屋へ向かった。ぬるいビールの喉ごしと、浮ついた夢や少しばかりの諦念が混じった近況報告と、もはや昔のような距離には近づけない寂しさと、車窓から見える薄ぼけた赤色に染まる富士山を背に釣りを楽しむおっちゃん達の横顔が、感覚として残っている。
成人式は小学校の同窓単位で執り行われた。中学から地元の公立ではなく私立へ進んだ私と彼は、残りの大部分の同級生とは違う想い出の層にいることを知る。こちらとあちらは半透明のガラスで遮られていて、彼らの輪郭を見ることはできても身を寄せることは決して許されなかった。孤独といえば孤独だが、そういう人生を選んできて今もその延長線上にいると改めて実感した。結局はどこまでも一人なのだ。それでも同級生の一人は鎌倉でパティシエとして店を開き、一人は子どもを育て、一人はホストとして日々を邁進しているという。それぞれがそれぞれに生きているということが、確かな安堵感をもたらしてくれた。重ならなくても、それぞれがそれぞれに在るということが。
夜も更けて、なにかの縁の巡り合わせか、初恋の女の子と飲む機会を得た。昔からどこかしら影のある子だったし、当時はそこに惹かれたのだが、影が後戻りできない方向へ深くなっていると感じ、哀しくなった。終電間際に地下鉄のホームで別れてから「ありがとう」とひとことメールを送ってみた。今でもその返事は返ってこない。
あれから2年が経った。バルザック曰く、「結局のところ、最悪の不幸は決して起こらない。たいていの場合、不幸を予期するから悲惨な目に会うのだ」。結果を予想して縮こまって、踏み出せずに多くの物事を見過ごしてきたのだろう。つながっているんだという感覚に怯えて、逆につながりから身を閉じてきたのだろう。今は、そしてこれからますます、立ち止まらずに踊っていたいと思う。Baudelaireはいう。「人生とは、病人の一人一人が寝台を変えたいという欲望に取り憑かれている一個の病院である」。おそらくそうなのだろう。ただ、ナースコールを押しても誰もやってこない。自分が踊り続けていれば、この病室の中で、何かが変わってゆく。少なくとも病室の窓から毎日一定の時間だけ射し込む陽の当たる場所がある。今はまだそう思えるし、思えるんだからそれに賭けてみたい。昔メモした写真家星野道夫さんの言葉を再び引っ張りだこして、このとりとめなのない回想の蓋を閉めてみる。
「星野さん、とても感動する光景や景色や瞬間に出会ったとき、どうすればそれを人に伝えられるのだろう。写真で切り取ること?言葉にすること?それとも‥」星野:「自分が変わることだよ」


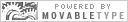
***→