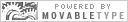[Waltz for Debby]
by Bill Evans.
ジャズ史上のひとつの最大傑作。あらゆる意味でジャズの中で最も聴きやすく、かつ、心の角をふっと取る力がある一枚。誰にでも必ずオススメできるのは、この一枚だけ。ちなみにリンク先でちょぴっと聴ける。
・ Music(7)
・ コアな生活情報(6)
・ ニュース/社会(23)
・ 雑記(11)
・ 大学生活と学問と語り(36)
・ 旅/日本/世界(3)
・ 恋愛系のはなし(23)
・ とりあえず究極の恋愛論Final
・ とりあえず究極の恋愛論part.4
・ とりあえず究極の恋愛論part.3
・ とりあえず究極の恋愛論part.2
・ とりあえず究極の恋愛論part.1
・ ニュースを観てマゾ/サドの欲望を満たす
・ あなたが触れて、はじめてわたしが存在する
June 14, 2004
とりあえず究極の恋愛論 - 補講
とりあえず究極の恋愛論Finalでは、抽象的に抉り出された恋愛の構造(恋愛論)ではなく、恋愛の経験その一瞬一瞬のうち、たったひとつの物語にこそ恋愛の本質があることを述べました。それでも懲りないあなたにおくる、とりあえず究極の恋愛論ブックガイド。
続きを読む...June 13, 2004
とりあえず究極の恋愛論Final
 大雑把にいえばとりあえず究極の恋愛論part.1では恋愛に関する個人の心理的側面を、part.2では社会的側面を、part.3では実践的側面を、part.4では哲学的側面を語ってきました。さていよいよ最終章。恋愛論のまとめと、実際の恋愛そのものについて。おそらくこれが恋愛の本質。
大雑把にいえばとりあえず究極の恋愛論part.1では恋愛に関する個人の心理的側面を、part.2では社会的側面を、part.3では実践的側面を、part.4では哲学的側面を語ってきました。さていよいよ最終章。恋愛論のまとめと、実際の恋愛そのものについて。おそらくこれが恋愛の本質。
June 12, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.4
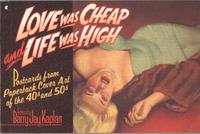 とりあえず究極の恋愛論part.1で「相手を好きになるとはどういうことか」、part.2で「社会制度として恋愛」、part.3で「相手を惚れさせるには?」とあれこれ書いてきました。今回は「愛」のいささか深い次元についてのおはなし。哲学的議論嫌いな方にはキツい記事かもしれません。無理ならパスしてください。ただ、恋愛と芸術をつなげる場合や、愛を深く論じる際には必要な話かなという気もします。次回フィナーレの予定。――「神様が僕を見るように、僕が彼女を見てあげることができるとき、僕は彼女を愛しているんだ」
とりあえず究極の恋愛論part.1で「相手を好きになるとはどういうことか」、part.2で「社会制度として恋愛」、part.3で「相手を惚れさせるには?」とあれこれ書いてきました。今回は「愛」のいささか深い次元についてのおはなし。哲学的議論嫌いな方にはキツい記事かもしれません。無理ならパスしてください。ただ、恋愛と芸術をつなげる場合や、愛を深く論じる際には必要な話かなという気もします。次回フィナーレの予定。――「神様が僕を見るように、僕が彼女を見てあげることができるとき、僕は彼女を愛しているんだ」
June 08, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.3
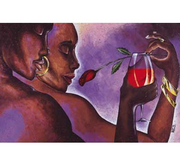 とりあえず究極の恋愛論part.1とpart.2の続編エントリー。もしこれを読むならば先にそれらを読んでくださいませ。本当に書きたいことはまだまだ書けずじまい。ここで、これまで書いたことを少々実践的なことにつなげてみたい。つまり、「相手を惚れさせる」「恋愛を長続きさせる」にはどうすればいいのか?
とりあえず究極の恋愛論part.1とpart.2の続編エントリー。もしこれを読むならば先にそれらを読んでくださいませ。本当に書きたいことはまだまだ書けずじまい。ここで、これまで書いたことを少々実践的なことにつなげてみたい。つまり、「相手を惚れさせる」「恋愛を長続きさせる」にはどうすればいいのか?
June 07, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.2
 とりあえず究極の恋愛論part.1を先に読んでくださいませ。ヨゴレに徹して恋愛論を書いてます。
とりあえず究極の恋愛論part.1を先に読んでくださいませ。ヨゴレに徹して恋愛論を書いてます。
さて、今回は彼氏/彼女という「制度」について考えてみたい。いわば恋愛の制度論だ。言い換えれば、相手を好きということと、相手と付き合うということに違いはあるのか?セフレと恋人の違いは?
続きを読む...June 06, 2004
とりあえず究極の恋愛論part.1
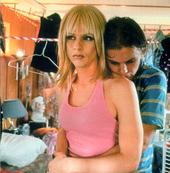 今日また不思議なセリフを聴いてしまった、「あの人は私のこと好きなんじゃなくて、恋してる自分に酔ってただけなんだよ、結局は」。強烈な違和感を感じた。何だ、それは。相手を好きだということと、相手を好きな自分が好きということは、全く同じ。ではそもそも好きってなんだ?恋って何だ?愛ってなんなんだ?「とりあえず」究極の恋愛論。1.なぜわたしは誰かを好きになる?2.制度としての恋愛論 3.惚れさせるには?4.恋愛と永遠――哲学・芸術・宗教と「愛」5.「好き」と「愛」の違い・恋愛の本質とは何か、という流れで。今日は1.について。
今日また不思議なセリフを聴いてしまった、「あの人は私のこと好きなんじゃなくて、恋してる自分に酔ってただけなんだよ、結局は」。強烈な違和感を感じた。何だ、それは。相手を好きだということと、相手を好きな自分が好きということは、全く同じ。ではそもそも好きってなんだ?恋って何だ?愛ってなんなんだ?「とりあえず」究極の恋愛論。1.なぜわたしは誰かを好きになる?2.制度としての恋愛論 3.惚れさせるには?4.恋愛と永遠――哲学・芸術・宗教と「愛」5.「好き」と「愛」の違い・恋愛の本質とは何か、という流れで。今日は1.について。
1.なぜわたしは誰かを好きになる?
便宜的に愛/恋の区別はひとまず保留。人に恋心を抱くとき、あえて分けるならば、その理由はおおまかに二つあるといえよう。一つはa. 性的魅力にまつわるもの、もう一つはb. (相手が)自分のアイデンティティを与えてくれることに関するもの。
a. 性的魅力は、人間のいわば「本能」と呼ばれるものに関連している。 人間も進化を経て誕生したひとつの「種」/ヒトという動物であるならば、恋愛感情も進化的に形づくられてきたはず。女性ホルモン、エストロゲンが多いと胸が大きくなる。だから胸が大きい女性は人気が出やすい(「出やすい」ということは、それがすべてではないということ。これは人間の救いかも)。セックスしたいという感情。相手の体臭にドキドキすること。男らしい筋肉に感じるドキドキ。セックスすると好きになる。酔った勢いでしたキスの記憶が頭から離れなくて、その人のことを好きになる。
b. (相手が)自分のアイデンティティを与えてくれることに関するもの。これはつまり「優しいからあの人が好き」だとか「一緒にいると素の自分でいられる」だとか「その人に会うために生きている」だとか「あの人は尊敬できる」だとか「あたしの帰る場所だからね」だとか「あいつのこと放っておけないんだよな」とか「だって超カッコイイし(可愛いし)」とか「趣味があうんだよね」、「オシャレだから」なんて話に関するもの。
続きを読む...June 04, 2004
ニュースを観てマゾ/サドの欲望を満たす
 私たちはニュースをよくみる。新聞を読む。何故だろう。実に不思議だ。ニュースに映し出される現実は、圧倒的に「不幸の手紙」が多い。幸せなニュースを、暗いニュースが凌駕する。地震。爆弾。テロ。殺人事件。死体。泣き声。悲痛な顔。叫び。
私たちはニュースをよくみる。新聞を読む。何故だろう。実に不思議だ。ニュースに映し出される現実は、圧倒的に「不幸の手紙」が多い。幸せなニュースを、暗いニュースが凌駕する。地震。爆弾。テロ。殺人事件。死体。泣き声。悲痛な顔。叫び。
「ニュースは子供に見せないのよ。だって教育上悪いじゃない」という親がいるという。私たちの幸せな食卓に、あるいは心地よい朝の目覚めに、突然割り込む「不幸な手紙」。日常の生活世界、なにげない瞬間に、突然割り込む暴力の知らせ。このふたつの間の、感覚の圧倒的な断絶。あまりに私の夕食と小学校殺傷事件はズレている。イラクもズレている。
なぜ私はあえて「不幸の手紙」を自ら進んで観るのだろうか。世界を知りたいという欲望が強いから?世界を知っておかないと不安になるから?でも考えてみて欲しい。何も社会的「事件」が起きなかった日のニュースのことを。どこかで祭りが行われた。誰々が結婚した。スポーツの話題。あなたは、満たされていないのでは?何か物足りないのでは?つまらない、のでは?
私は「不幸の手紙」を待っている。「不幸の手紙」を求めてテレビをつける。他人の不幸を待ち望んでいる。イラク問題の時に「自己責任が大切だ!」あるいは「3人を非難するなんて信じられない!」という言説に違和感を感じ、それは「生活世界から目をそらして<大きなこと>に酔っているのでは?」と指摘した(参考)のは、このような背景もあると感じたからだ。それは何よりもまず、私の、自分の、マゾ的な卑しい欲望である。私は「不幸の手紙」が無ければ満たされないからだになってしまったのかもしれない。その上で、「不幸」に対して自分が何を出来るかを考えて、今度は逆にサド的欲望を満たしているのかもしれない。どこにゆけば良いのだろう。それでもそのまま歩けというのならば、誇らしげに持てる力をすべて込めながら歩いていってやる。
June 02, 2004
あなたが触れて、はじめてわたしが存在する
 ラカンについて考えていてふと面白いことを知ったので。いわば実験心理学的な「赤ちゃん学」から精神分析家・ラカンの「鏡像段階論」を検討するとどうなるか―――ラカンの言うように、わたしは鏡を見ることによってはじめて「自分はひとつの統一された形を持った<私>である」ことを知るのか?それとも実験心理学的にはラカンの鏡像段階論は誤りであるのか?赤ん坊を持つ母親の方もこれは要注目ですよ。あるいは最後まで読めばセックスの凄さの理由が少しはわかるかも。
ラカンについて考えていてふと面白いことを知ったので。いわば実験心理学的な「赤ちゃん学」から精神分析家・ラカンの「鏡像段階論」を検討するとどうなるか―――ラカンの言うように、わたしは鏡を見ることによってはじめて「自分はひとつの統一された形を持った<私>である」ことを知るのか?それとも実験心理学的にはラカンの鏡像段階論は誤りであるのか?赤ん坊を持つ母親の方もこれは要注目ですよ。あるいは最後まで読めばセックスの凄さの理由が少しはわかるかも。
国際的に活躍する極めて優秀な心理学者、下條信輔による『まなざしの誕生――赤ちゃん学革命』という本がある。主に実験心理学的に「赤ちゃん」を考察した、実に面白い一冊だ。その一冊から「鏡と<鏡を見る私>」というテーマに関して興味深いところを抜き出しておく。
1)猫・犬・鳥類・猿・は鏡の中に映っているものが実は自分の分身であるということを認識できない。 2)チンパンジー・オラウータンは自己認識ができる。3,4日くらい鏡に慣れると、鏡の中の自分に対して「まるでほかの個体がそこにいるかのような<社会的反応>がなくなり、人間と同じような<自分に対する反応>を示すようになる」。 3)これが本当の意味での「自己認識」かどうか確認するため奇想天外な実験が行われた。「まず、鏡に十分慣れ親しませてから、麻酔でチンパンジーは眠らされる。次に、完全に無味無臭で、皮膚につけてもゴワゴワしたりしないような特別な染料を使い、チンパンジーの顔の一部を真っ赤に、けばけばしく化粧してしまう」。この哀れな<歌舞伎役者>は、目を覚まして鏡を見ると、「決して鏡の中の顔に手を伸ばしたりはせず、ほんものの(自分の)顔の赤い部分をこすったり、ひっかいたり、またそのあとでその指をじっとみつめる、鼻へ持っていく、などの行動がみられた」。 4)生まれたときから完全に隔離されて育てられたみなし子チンパンジーに同様の実験をしても、このような自分自身に対する探索の行動はみられなかった。 5)このことは自己認識の芽生えが、他人(他猿)の存在を前提としていることを示す」。
さらにここからが面白い。母親、必見。この論文に先立った実験で、研究者は、生後すぐに親から隔離されて育てられた、一歳半前後の幼いチンパンジー三匹を、ふたつのオリで育てた。三匹のうち二匹は同じオリの中で、自由にじゃれあったり、取っ組み合ったりして遊ぶことを許された。残りの一匹はもうひとつのオリに入れられ、ほかの二匹と一緒に遊ぶことはできなかったが、彼らの姿は見ることができた。つまり触れあいはないが視覚では他者を認識している状態だ。このようにして三匹を一ヶ月ほど育てた後、鏡に十分慣れ親しませた上で、例の<歌舞伎役者>のやりかたで実験を行った。その結果、一緒に育てられた二匹のチンパンジーは、ふつうの個体と同じような自己認識の反応(ex.自分の頬をひっかく)をみせたが、対照的に、ひとりぼっちのチンパンジーではそのような反応がまったく見られなかった。つまり、鏡の中に「自分」を見出すためには、視線による社会的交流だけでは不十分で、からだの直接的な接触がなくてはならないことがわかるのだ。
これはきわめて重要なことを示唆している。つまり、からだの接触なしで育てられた子供は、「自分」をはっきりと確立することはできない。そして他人と社会的に正常な交渉を持つことができなくなるだろう。いかにスキンシップが大切か。文字通りの、スキンシップ。
では、なぜこういう結果になるのか。「自分の腕をつまんでみたときと、他人の腕をつまんでみたときとでは――からだに起こる感覚はまったく違う。<さわり>同時に<さわられている>感覚があるのは、自分のからだだけである」。そして腕は鏡がなくとも自分で見ることができる。鏡がなくとも自己認識は成立しうるだろう。また「自分の頬や背中をつまんだときは、直接目には見えないけれども、からだに起こる感覚としてはやはり、自分の腕に似ているといえるだろう」(サルトルなどの「即自」と「対自」の概念?)。つまり、「子供にとって、一番教育的なものは、自分自身やほかの人たちのからだである」
文字通りの「身体感覚」が<わたし>の根底にあり、私を<わたし>たらしめている。見える腕と感じられる腕との関係。さあ、ラカンの鏡像段階論を考えてみよう。ラカンのいうように「鏡体験」のおかげで自己認識が成立するのではない。むしろ反対に、体感覚を通じた学習の結果、「鏡像認知」が可能になるのである。からだが先立つ。またラカンのいうように、ばらばらの身体興奮の集まりにすぎないいわば人間以前の存在が、鏡の中にまとまった像としての<わたし>を発見するのではない。すなわち「感覚同士が結びつく」のではなくて、「感覚同士ははじめから結びついている」。自分自身のからだと他人のからだをぶつけあって遊ぶことが、未分化の世界から分化した世界へと進む、決定的な足がかりとなる。身体感覚を通じて<わたし>を知ってはじめて、主体は鏡の中に<わたし>を発見することができるのだ。
さて、だからといって、ラカンの理論はまやかしだなどと言うつもりは毛頭ない。ラカンの理論はむしろ記号論的な意味で、すなわち<わたし>の内実は<他者>に私を重ね合わせることによってしか生まれてこないという意味で、また象徴が持つ役割を言説的に権威づける意味で、きわめて意義を持っているように思われる。<象徴界><対象a>は「使える」概念だ。だがしかし、発達論的な意味において、あるいはそもそもの人間の根源としてのカオスを考える上で、「鏡像段階論」に依拠しすぎることは少々危ういといわざるをえない。思想的に意味の地平を切り拓く上では有効であっても、それに基づいて実際に治療的介入を行うことには少々抵抗を感じてしまう。
セックスが根源的というのはこのような意味においてなのかもしれない。スキンシップこそが原初の私の感覚を与えてくれるものであるならば、肉体的な触れ合いにこそわたしは安らぎと戦慄を感じることができるだろう。ラカンの話にしろセックスの話にしろ、諸刃の剣をうまく振りかざしながら自分なりの意味体系を築いてゆきたいと強く感じた、6月1日。原宿駅にはもう紫陽花。